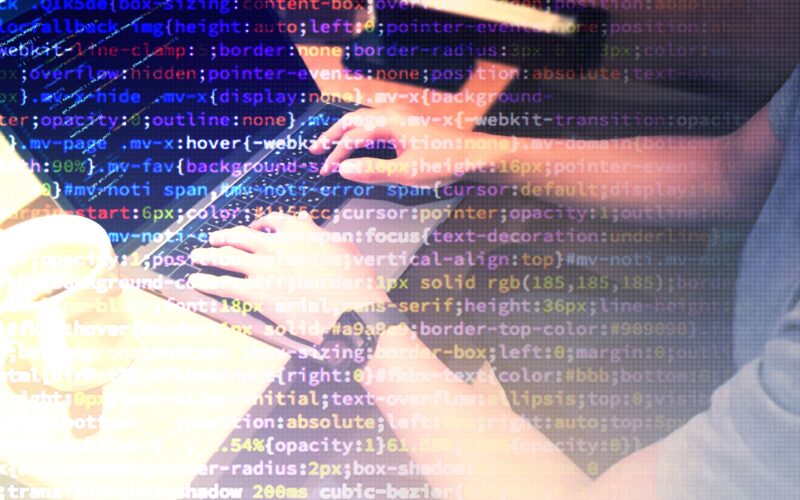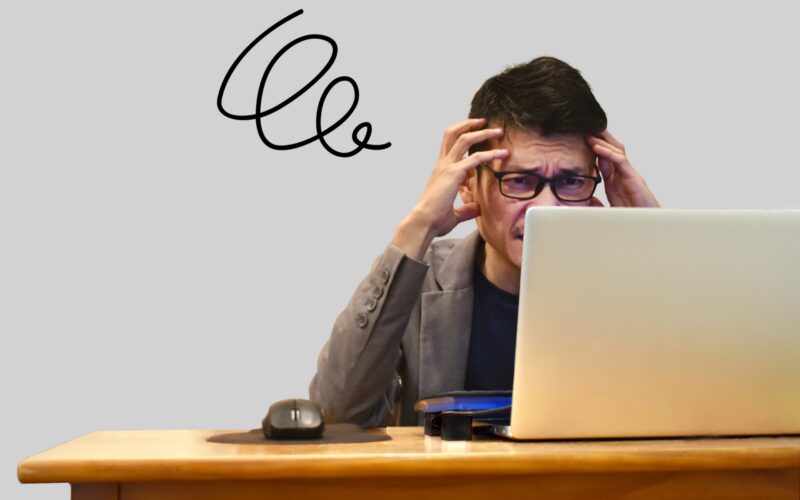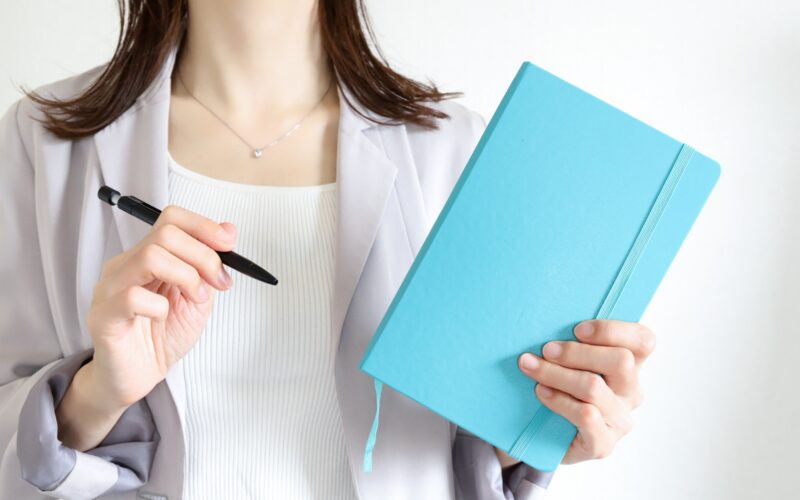はじめに:あなたの会社の「CO2」、見えない“9割”を、放置していませんか?
「我が社は、工場の省エネを、徹底し、CO2排出量を、10%削減しました」
「社用車を、電気自動車(EV)に入れ替え、環境への貢献を、果たしています」
あなたの会社でも、このような、環境への取り組みを、誇らしく、社内外に、アピールしているかもしれません。
その、真摯な努力は、間違いなく、尊いものです。
しかし、もし、その削減努力が、あなたの会社が、排出する、温室効果ガス全体の、わずか「1割」にしか、相当しないとしたら…?
そして、残りの「見えない9割」が、あなたの会社の、サプライチェーン全体に、広がり、気づかぬうちに、地球環境と、あなたの会社の、未来の経営リスクを、静かに、しかし、確実に蝕んでいるとしたら…?
DXと、サステナビリティ(SX)が、経営の、両輪となった現代。
企業が、気候変動という、地球規模の課題に、本気で向き合う上で、もはや、避けては通れない、グローバルな「共通言語」。
それこそが、自社の事業活動だけでなく、サプライチェーン全体で、排出される、温室効果ガスを、包括的に、算定・管理する「サプライチェーン排出量(スコープ1・2・3)」という、考え方です。
この記事は、「ESG投資家から、スコープ3の開示を、求められているが、そもそも、それが何か、分からない」「自社の、本当の環境負荷を、把握し、本質的な、削減努力を、始めたい」と考える、すべての、先進的な経営者、サステナビリティ担当者、そして、調達・生産・物流の、最前線に立つ、実務家のためのものです。
本稿では、この、極めて重要で、しかし、複雑な「サプライチェーン排出量」について、その、基本的な概念から、具体的な算定方法、そして、削減への、戦略的アプローチまでを、体系的に解き明かしていきます。
この記事を読み終える頃には、あなたは以下のものを手にしているはずです。
- スコープ1・2・3の、明確な定義と、その、戦略的な意味合いの、深い理解
- 難解な「スコープ3」の、15のカテゴリーと、その、具体的な算定方法の、全体像
- DX(デジタル技術)を、駆使して、排出量を、効率的に「見える化」し、「削減」するための、実践的なヒント
- そして、この「カーボンアカウンティング(炭素会計)」のスキルが、あなたの市場価値を高める最高のスキルアップとなり、未来のキャリアアップや転職に、どう繋がるかという、明確なビジョン
サプライチェーン排出量の、算定と削減は、単なる、環境報告のための、面倒な作業では、ありません。
それは、自社の、ビジネスの、隠れたリスクと、新しい、イノベーションの機会を、発見するための「宝探しの地図」を手に入れる、行為なのです。この、新しい地図を読み解く能力は、最高のリスキリングです。
さあ、自社の「見える化」の、その先へ。
サプライチェーン全体の、未来に、責任を持つ、真の、サステナビリティ経営への、扉を、ここから開きましょう。
1. 全ての、土台となる「GHGプロトコル」と、スコープ1・2・3の、基本概念
サプライチェーン排出量について、語る上で、全ての「ルールブック」となるのが、国際的な、基準である「GHGプロトコル」です。
まずは、この、グローバルスタンダードの、基本的な考え方と、スコープ1・2・3という「分類」の、意味を、正しく理解することから、始めましょう。
1-1. GHGプロトコル:温室効果ガス排出量の「世界標準」
- GHGプロトコル (Greenhouse Gas Protocol) とは?
- WRI(世界資源研究所)とWBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)という、2つの、国際的な機関が、中心となり、開発した、温室効果ガス(GHG)排出量の、算定と、報告に関する、国際的な基準。
- 今や、世界中の企業や、政府が、GHG排出量を、算定・報告する際の、事実上の「グローバルスタンダード」となっており、後述する、TCFDや、CDPといった、国際的なイニシアチブも、このGHGプロトコルに、準拠しています。
- なぜ「標準」が、重要なのか?
- もし、各社が、バラバラの、計算方法で、CO2排出量を、公表していたら、私たちは、A社とB社の、環境パフォーマンスを、客観的に「比較」することが、できません。
- GHGプロトコルという「共通の、物差し」があることで、企業間の、比較可能性と、情報の、信頼性が、担保されるのです。
1-2. スコープ1・2・3の、基本的な「切り分け」
GHGプロトコルは、企業活動に伴う、GHG排出量を、その排出源に応じて、3つの「スコープ(範囲)」に、分類しています。
これを、自社を中心とした「輪」のイメージで、捉えると、非常に分かりやすいです。
1-2-1. スコープ1 (Scope 1):自社の「直接」排出
- 定義:
- 事業者自らによる、温室効果ガスの「直接排出」。
- アナロジー:
- 「自分の家(自社)の、煙突や、排気管から、直接、出てくる煙」
- 具体的な、排出源:
- 燃料の、燃焼:
- 自社の、工場で使う、ボイラーの燃料(都市ガス、重油など)の燃焼。
- 自社が、所有する、営業車や、トラック(社有車)の、ガソリン・軽油の燃焼。
- 工業プロセス:
- 化学製品の、製造プロセスや、セメントの製造などで、発生するGHG。
- 燃料の、燃焼:
- 算定の、容易さ:
- 比較的、算定が容易。燃料の、使用量や、車両の走行距離といった、自社で、管理しているデータから、直接、計算することができます。
1-2-2. スコープ2 (Scope 2):購入した「エネルギー」が、作る、間接排出
- 定義:
- 他社から、供給された、電気、熱、蒸気の使用に伴う「間接排出」。
- アナロジー:
- 「自分の家で、使う電気を、作るために、遠くの“発電所”で、排出される煙」
- 具体的な、排出源:
- 購入した、電力:
オフィスや、工場で、使用する、電力会社から、購入した電力。 - 購入した、熱・蒸気:
地域熱供給事業者などから、購入した熱や蒸気。
- 購入した、電力:
- 算定の、容易さ:
- スコープ1と、同様に、算定が比較的、容易。電力会社からの、請求書に記載された、電力使用量に、電力会社ごとの、排出係数を、掛け合わせることで、計算できます。
1-2-3. スコープ3 (Scope 3):サプライチェーン全体の、全ての「その他」の間接排出
- 定義:
- スコープ1、スコープ2以外の、全ての「間接排出」。
- すなわち、自社の、サプライチェーン(バリューチェーン)全体における、上流から、下流までの、あらゆる活動に伴う排出。
- アナロジー:
- 「自分の家に、商品が届くまでの、全てのプロセス、そして、家から出た後の、全てのプロセスで、排出される、あらゆる煙」
- 具体的な、排出源の例:
- 上流 (Upstream):
- 購入した、製品・サービス:
原材料の、調達、部品の製造 - 輸送・配送:
外部の、物流会社に委託している、輸送 - 従業員の、通勤・出張
- 購入した、製品・サービス:
- 下流 (Downstream):
- 販売した、製品の「使用」:
顧客が、自社の、自動車や、家電を、使用する際に、消費する、ガソリンや電力。 - 販売した、製品の「廃棄」:
顧客が、製品を使い終えた後、それを廃棄・リサイクルする際の、排出。
- 販売した、製品の「使用」:
- 上流 (Upstream):
- 算定の、難易度:
- 極めて、算定が困難。なぜなら、これらの排出は、自社の、直接的な管理の、及ばない、サプライヤーや、顧客、そして、その先の、社会全体で、発生しているからです。
この、スコープ1・2という「自社の、直接的な責任範囲」と、スコープ3という「サプライチェーン全体の、間接的な責任範囲」を、明確に区別し、そして、その全てを、包括的に捉えること。
それこそが、現代の、サステナビリティ経営の、出発点なのです。
2. なぜ「スコープ3」が、DX時代の“ラスボス”なのか?
「スコープ1と2なら、なんとか計算できそうだ。しかし、スコープ3は、あまりにも広大で、複雑すぎる。なぜ、そんな、管理不可能なものまで、算定する必要があるのか?」
多くの、実務担当者が、そう感じるのも、無理はありません。
しかし、今、世界の潮流は、この、最も困難な「スコープ3」にこそ、企業の、真の、サステナビリティへの、本気度が表れる、と考えています。
2-1. 理由①:企業の、総排出量の、大部分を占める、という事実
- 氷山の、一角:
- 多くの、業種、特に、製造業や、小売業において、自社が直接管理できる、スコープ1と2の合計は、サプライチェーン排出量全体の、わずか1〜2割に過ぎません。
- 残りの、8〜9割は、スコープ3、すなわち、自社の管理外の、サプライチェーン上で、発生しているのです。
- 意味すること:
- もし、企業が、スコープ1と2の、削減だけに、取り組み、スコープ3から、目を背けているとしたら、それは、海に浮かぶ、氷山の、水面に出ている、ほんの一角だけを、削っているようなものです。
- 水面下に、隠された、巨大な氷山(スコープ3)に、手をつけない限り、地球温暖化への、本質的な、貢献は、できません。
2-2. 理由②:投資家と、顧客からの、厳しい「目」
- TCFD (気候関連財務情報開示タスクフォース):
- G20の、要請を受けて、設立された、国際的なイニシアチブ。
- 企業に対して、気候変動が、自社の財務に与える「リスク」と「機会」を、具体的に、開示することを、求めています。
- 日本でも、プライム市場の、上場企業には、このTCFDに、準拠した、情報開示が、実質的に、義務化されています。
- CDP (旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト):
- 機関投資家が、連携して、企業に対して、環境情報を、開示するように、求める、国際的なNGO。
- 投資家が、見ているもの:
- これらの、国際的な、枠組みは、企業に対して、スコープ1、2だけでなく、スコープ3の、排出量の開示を、強く要求しています。
- 投資家は、スコープ3を、開示できない企業を、「自社の、サプライチェーンに、潜む、気候変動リスクを、把握できていない、ガバナンスの、低い企業」と、見なします。
2-3. 理由③:「リスク」と「機会」の、宝庫である
スコープ3の、算定は、困難な、作業ですが、それは、単なる「コスト」や「義務」では、ありません。
自社の、ビジネスを、新しい視点で見つめ直し、これまで見えなかった「リスク」と「事業機会」を発見するための、最高の「レンズ」となり得るのです。
- リスクの、発見:
- 「自社の、主要な、一次サプライヤーが、気候変動による、水害リスクの、極めて高い、地域に、集中している」
- 「自社の、製品は、顧客が、使用する段階で、多くのエネルギーを、消費しており、将来の、エネルギー価格高騰や、炭素税の導入によって、競争力を失う、リスクがある」
- 事業機会の、発見:
- 「サプライヤーと、協働して、省エネ技術を、導入支援すれば、自社のスコープ3を、削減できるだけでなく、サプライヤーの、コスト削減にも、貢献でき、パートナーシップを、強化できる」
- 「製品の、エネルギー効率を、劇的に改善する、新しい技術を、開発すれば、それが、新しい、競争優位性となる」
このように、スコープ3という、困難な「ラスボス」に、向き合うことこそが、企業を、受動的な「報告者」から、能動的な「変革者」へと、進化させる、重要な、きっかけとなるのです。
3.【算定実践編①】スコープ3の、全体像と「上流」の、カテゴリー
ここからは、いよいよ、スコープ3の、具体的な「算定方法」について、見ていきましょう。
GHGプロトコルは、スコープ3を、15の「カテゴリー」に、分類しています。
全てを、一度に、完璧に算定するのは、困難です。まずは、自社の事業にとって、関連性が高く、排出量が大きいと、想定されるカテゴリーから、優先順位をつけて、算定に着手するのが、現実的なアプローチです。
【算定の、基本計算式】
全てのカテゴリーに、共通する、基本的な計算式は、極めてシンプルです。
排出量 = 活動量 × 排出原単位
- 活動量:
- 事業者の、活動の規模に関する、データ。(例:購入した、原材料の「重量(t)」、輸送した貨物の「重量(t)×距離(km)」、従業員の「出張費用(円)」)
- 排出原単位:
- 活動量あたりの、GHG排出量。(例:「鉄鋼 1tあたりの、CO2排出量」「貨物輸送 1tkmあたりの、CO2排出量」「1円の、購入金額あたりの、CO2排出量」)
- この、排出原単位は、環境省などが、データベースとして、公開しており、それを利用することができます。
ここでは、15のカテゴリーを「上流(Upstream)」と「下流(Downstream)」に分け、特に重要なものを、解説します。
3-1. カテゴリー1:購入した製品・サービス (Purchased Goods and Services)
- 概要:
- 事業者が、その年に購入・取得した、全ての「製品(原材料、部品など)」と「サービス(外部委託費、コンサルティング料など)」の、製造・提供段階までに、排出されたGHG。
- なぜ、重要か?
- 多くの、製造業や、小売業にとって、スコープ3の中で、最も大きな、割合を占める、最重要カテゴリー。
- 算定方法:
- 方法①(最も、簡易):金額ベース
- 購入した、製品・サービスの「金額(円)」に、産業連関表に基づく、排出原単位(円あたりの、排出量)を、掛け合わせる。
- 方法②(より、精緻):重量ベース
- 購入した、原材料などの「重量(t)」や「数量」に、物質ごとの、排出原単位(重量あたりの、排出量)を、掛け合わせる。
- 方法③(最も、理想):サプライヤー固有値
- サプライヤーから、直接、その製品の、CO2排出量データ(カーボンフットプリント情報)を提供してもらい、それを積み上げる。
- 方法①(最も、簡易):金額ベース
- データ収集の、課題:
- 購入している、品目数が、膨大であり、全ての、重量や、金額を、正確に把握することが、困難。
- サプライヤーから、正確な、排出量データを、入手することは、現状では、非常に難しい。
3-2. カテゴリー3:スコープ1,2に含まれない燃料・エネルギー活動
- 概要:
- スコープ1,2で、算定した、燃料や、電力について、その「採掘、精製、発電、送電」といった、上流のプロセスで、発生した排出量。
- 算定方法:
- 自社が、使用した燃料や、電力の量に、燃料種別、あるいは、電力会社ごとの、上流工程の、排出原単位を、掛け合わせる。
3-3. カテゴリー4:輸送、配送(上流)
- 概要:
- 自社が、購入した製品の、サプライヤーから、自社までの輸送。
- および、自社内の、拠点間の輸送のうち、他社の、輸送事業者に、委託している部分。
- 算定方法:
- 輸送する「貨物の、重量(t)」と「輸送距離(km)」を、把握し、輸送モード(トラック、鉄道、船、航空)ごとの、排出原単位(tkmあた年の、排出量)を、掛け合わせる。
- データ収集の、課題:
- 全ての、輸送について、正確な、重量と距離を、把握することは、困難な場合が多い。その場合は、輸送にかかった「燃料使用量」や「金額」から、推計することも可能。
3-4. カテゴリー5:事業から出る廃棄物
- 概要:
- 自社の、事業活動から、発生した、廃棄物の「輸送」と「処理(焼却、埋立など)」に伴う排出。
- 算定方法:
- 廃棄物の、種類ごとの「重量(t)」に、処理方法ごとの、排出原単位を、掛け合わせる。
3-5. カテゴリー6:出張
- 概要:
- 従業員の、出張に伴う、移動(飛行機、鉄道、タクシーなど)と、宿泊に関する排出。
- 算定方法:
- 移動:
各交通機関の、移動距離(人km)に、排出原単位を、掛け合わせる。 - 宿泊:
宿泊数(人泊)に、排出原単位を、掛け合わせる。 - 簡易的には、旅費交通費の「金額」から、推計することも可能。
- 移動:
3-6. カテゴリー7:雇用者の通勤
- 概要:
- 全ての、従業員の、自宅から、職場までの「通勤」に伴う排出。
- 算定方法:
- 従業員への、アンケートなどで、通勤手段(電車、バス、自家用車など)と、片道の距離を、把握する。
- 「従業員数 × 通勤手段ごとの、年間勤務日数 × 往復距離 × 排出原単位」で、算定。
4.【算定実践編②】スコープ3の「下流」の、カテゴリーと、削減アプローチ
次に、自社の、事業活動の「後」の、プロセスで発生する、「下流(Downstream)」の、排出について、見ていきましょう。
ここは、自社の、製品や、サービスの、あり方そのものが、問われる、極めて戦略的な、領域です。
4-1. カテゴリー9:輸送、配送(下流)
- 概要:
- 自社から、顧客への、製品の輸送・配送のうち、他社の、輸送事業者に、委託している部分。
- 算定方法:
- 上流の、カテゴリー4と、同様。「貨物の、重量(t)」×「輸送距離(km)」を、基本とする。
- 削減アプローチ:
- ① 輸送効率の、向上:
- AI搭載のTMS(輸配送管理システム)を、活用し、最適な配送ルートを、設計する。
- 共同配送を、推進し、トラックの積載率を、向上させる。
- ② モーダルシフト:
- トラック輸送から、より環境負荷の低い、鉄道・船舶輸送へと、転換する。
- ③ EVトラックの、導入促進:
- 輸送パートナーに対して、EVトラックへの、切り替えを、働きかける。
- ① 輸送効率の、向上:
4-2. カテゴリー11:販売した製品の使用
- 概要:
- 自社が、販売した製品が、顧客によって「使用」される段階で、消費される、エネルギーに伴う排出。
- なぜ、重要か?
- 自動車、家電、産業機械といった、製品を、製造・販売するメーカーにとって、スコープ3の中で、最も大きな割合を占める、最重要カテゴリー。
- (例:自動車メーカーの、総排出量のうち、顧客が運転する際の、ガソリン燃焼による排出は、8割以上を占める)
- 算定方法:
- 「販売した、製品の、生涯における、総エネルギー消費量」を、推計し、それに、排出原単位を、掛け合わせる。
- 生涯エネルギー消費量 = 1台あたりの、年間エネルギー消費量 × 販売台数 × 平均使用年数
- 削減アプローチ:
- ① 製品の、エネルギー効率の、徹底的な改善(省エネ設計):
- これが、最も本質的な、削減アプローチ。
- ② エネルギー源の、転換:
- ガソリン車から、電気自動車(EV)へ。
- ③ 顧客の、使い方を、変える:
- 製品に、IoTを搭載し、顧客の、エネルギー使用状況を「見える化」し、省エネな、使い方を、促す。
- ① 製品の、エネルギー効率の、徹底的な改善(省エネ設計):
4-3. カテゴリー12:販売した製品の廃棄
- 概要:
- 自社が、販売した製品が、顧客によって、使用された後に「廃棄・処理」される段階での排出。
- 算定方法:
- 「製品の、総重量」と「廃棄方法(埋立、焼却、リサイクル)の、シナリオ」を、設定し、排出量を推計する。
- 削減アプローチ:
- ① 長寿命設計:
- そもそも、すぐに「ゴミ」にならない、長く使える、丈夫な製品を、設計する。
- ② リサイクルしやすい、設計:
- 分解しやすく、単一の素材で作られた、リサイクル性の高い、製品を、設計する。
- ③ 回収・リサイクルシステムの、構築:
- 使用済みの、製品を、自社で回収し、再生・再資源化する、サーキュラーエコノミーの、ビジネスモデルを、構築する。
- ① 長寿命設計:
これらの「下流」カテゴリーへの、取り組みは、単なるCO2削減に留まりません。
それは、自社の、製品開発の、あり方、そして、ビジネスモデルそのものを、持続可能な、未来へと、変革していく「攻めのGX」そのものなのです。
この、戦略的な、思考力と、実行力は、プロダクトマネージャーや、事業開発担当者のキャリアアップにおいて、決定的な、差別化要因となります。
5. DXは、いかにして「見えない排出量」を、見える化し、削減するか
ここまで見てきたように、サプライチェーン排出量、特に、スコープ3の算定と、削減は、膨大で、複雑な「データ」との、戦いです。
自社の、管理下にない、無数のサプライヤーや、顧客に関するデータを、いかにして、効率的に「収集」し、「分析」し、そして「アクション」に、繋げるか。
この、困難な課題を、解決するための、最強の武器こそが、DX(デジタルトランスフォーメーション)です。
5-1. データ収集の、壁を、乗り越える
- IoTと、ブロックチェーンによる、トレーサビリティ:
- IoTセンサーやRFIDを、製品や、輸送コンテナに取り付け、その、位置情報や、状態を、リアルタイムで、トラッキング。
- それらの情報を、改ざん不可能な、ブロックチェーン上に、記録することで、サプライチェーン全体の、物理的な「モノ」の動きと、それに伴うCO2排出量を、正確に、追跡します。
- サプライヤー連携プラットフォーム:
- クラウドベースの、プラットフォームを通じて、数千、数万のサプライヤーに対して、CO2排出量データの、提出を、一括で要請し、収集します。
- サプライヤー側も、簡単なインターフェースを通じて、データを入力でき、双方の、事務的な負担を、軽減します。
5-2. 算定・分析の、壁を、乗り越える
- GHG排出量、算定・可視化SaaS:
- 近年、企業の、スコープ1・2・3の排出量を、効率的に、算定・可視化・管理するための、専門的なSaaS(Software as a Service)が、次々と登場しています。
- 代表的なサービス:
- Zeroboard, Persefoni, Salesforce Net Zero Cloudなど。
- 主な機能:
- 排出原単位データベース:
環境省などが、公開する、膨大な排出原単位データベースを、標準搭載。 - データ連携:
会計システムや、購買システムと、API連携し、活動量データ(金額、物量など)を、自動で取り込み。 - 自動算定と、ダッシュボード:
取り込んだ、活動量と、排出原単位を、自動で掛け合わせ、スコープごと、カテゴリーごとの、排出量を、ダッシュボードで、リアルタイムに可視化します。
- 排出原単位データベース:
- AIによる、シミュレーションと、予測:
- AIが、可視化された、排出量データを分析し、「どの、削減施策が、最も、費用対効果が高いか」といった、削減シナリオを、シミュレーションし、最適な、打ち手を、提案します。
5-3. 削減アクションの、壁を、乗り越える
- デジタルツインによる、エコデザイン:
- 製品の、設計段階で、デジタルツインを活用し、その製品が、ライフサイクル全体で、排出するCO2量を、シミュレーション。環境負荷が、最小となるような、設計を、追求します。
- AIによる、生産・物流の最適化:
- スマートファクトリーにおいて、AIが、工場のエネルギー消費を、最適制御。
- TMS(輸配送管理システム)において、AIが、最適な配送ルートを、設計。
このように、DXは、サプライチェーン排出量の、算定と、削減という、極めて複雑な、パズルを解くための、唯一無二の「解法」を、提供してくれるのです。
これらの、ツールを、使いこなし、データに基づいて、サステナビリティ戦略を、推進できる能力は、これからの、ビジネスパーソンにとって、必須のスキルアップとなります。
6. まとめ:「炭素会計」のスキルは、あなたの、未来を照らす、新しい“専門性”
本記事では、DXと、サステナビリティが、交差する、最重要領域である、「サプライチェーン排出量(スコープ1・2・3)」について、その、本質的な重要性から、具体的な算定方法、そして、削減への、アプローチまで、あらゆる角度から、解説してきました。
サプライチェーン排出量の、算定と、削減への取り組みは、もはや、一部の、大企業や、環境部門だけの、専門的な、業務では、ありません。
それは、自社の、ビジネスが、地球環境と、どのように関わり、どのような影響を与えているのか、その「責任」と「可能性」を、客観的な「数字」で、語るための、新しい「ビジネスリテラシー」なのです。
財務会計が、企業の「経済的な、健康状態」を、示すように、この、GHG排出量の算定、通称「炭素会計(カーボンアカウンティング)」は、企業の「環境的な、健康状態」と「未来への、持続可能性」を示す、もう一つの、重要な「決算書」と言えるでしょう。
- スコープ3は、あなたの会社の、ビジネスモデルの「写し鏡」である。
- その、算定は、隠れた「リスク」と、新しい「機会」を、発見する、宝探しである。
- DXは、その、困難な、宝探しを、可能にする、唯一の、コンパスである。
- そして、この、新しい「会計スキル」を、身につけることは、あなたの、キャリアを、未来の、成長市場へと、導く、最高の「リスキリング」である。
この「炭素会計」の、専門知識と、実践経験は、あなたの、市場価値を、飛躍的に高めます。
サステナビリティ推進担当、ESGコンサルタント、SCM改革リーダーといった、専門職へのキャリアアップはもちろん、金融業界や、経営企画といった、領域への転職においても、極めて強力な、武器となります。
あなたが、日々、向き合っている、サプライチェーン。
その、一つひとつの、取引の、裏側には、どれくらいの、CO2が、隠れているのでしょうか。
その、見えない、コストを、可視化し、削減していく、知的な挑戦。
その、一歩が、あなたの会社を、そして、あなた自身のキャリアを、持続可能で、輝かしい、未来へと、導く、大きな、原動力となるはずです。