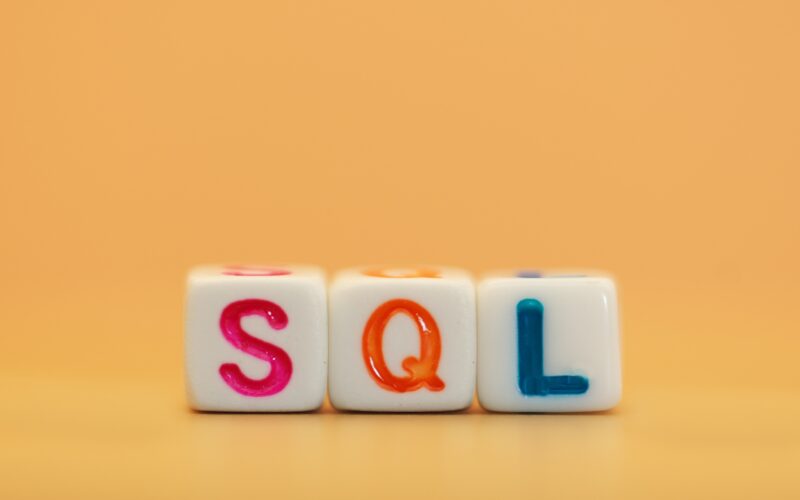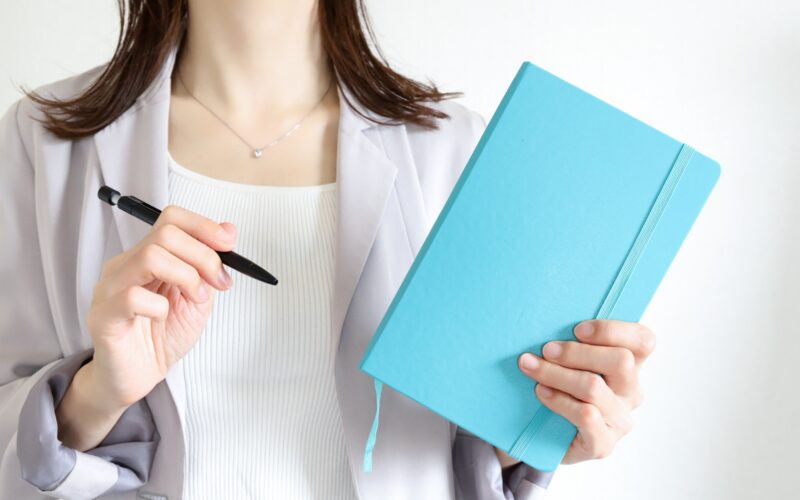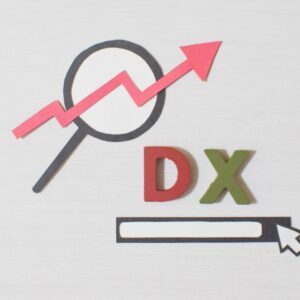はじめに:なぜ、あなたの会社のDXは進まないのか?
「我が社もDXを推進する!」
力強い号令と共に、多額の予算と人員を投じてスタートした、デジタルトランスフォーメーション(DX)プロジェクト。しかし、数ヶ月、あるいは数年が経過した今、その進捗はどうでしょうか。「期待した成果が出ていない」「現場から反発の声が上がっている」「導入したツールが誰にも使われていない」…そんな厳しい現実に直面してはいないでしょうか。
あなただけではありません。国内外の調査によれば、DXへの取り組みが「成功した」と評価できる企業は、全体のわずか2〜3割に過ぎないと言われています。多くの企業が、DXという名の、先の見えない航海で、座礁や遭難の危機に瀕しているのです。
しかし、嘆く必要はありません。なぜなら、他者の「失敗」は、我々にとって最も価値のある「学びの教科書」だからです。成功事例は、その企業の特殊な文脈に依存することが多く、必ずしも再現性がありません。しかし、失敗のパターンには、驚くほど共通した、普遍的な原因が潜んでいます。
この記事では、DX推進において多くの企業が陥りがちな、7つの典型的な「失敗の物語」を、具体的な事例として紹介します。そして、それぞれの物語から、我々が学ぶべき、成功への羅針盤となる「7つの教訓」を導き出します。これは、あなたの会社のDXを、失敗の航路から成功の軌道へと引き戻すための、実践的な航海図です。
1. 失敗事例①「目的の形骸化」- 高価なツールが“文鎮”と化す悲劇
【ケーススタディ:老舗アパレルA社の物語】
長年の店舗販売に依存し、EC化の遅れに危機感を抱いていたA社の経営陣は、「DXで顧客接点を強化する」という目標を掲げ、最新鋭のMA(マーケティングオートメーション)ツールとSFA(営業支援ツール)の導入を決定しました。数千万円の投資を行い、華々しくプロジェクトはスタート。しかし、1年後、そのツールはほとんど誰にも使われず、高価な“文鎮”と化していました。
現場の販売員は、日々の接客で手一杯で、煩雑なデータ入力を行う余裕も意欲もありませんでした。営業担当者も、これまで慣れ親しんだExcel管理の方が早いと、新しいツールを敬遠。結局、ツールから得られるデータは不完全で、当初期待していた「データに基づいた顧客へのアプローチ」は、絵に描いた餅に終わりました。
1-1. なぜ失敗したのか?「手段の目的化」という罠
A社の失敗の根本原因は、「DXの目的」と「ツールの導入」を取り違えてしまったことにあります。
彼らにとってのDXは、いつの間にか「MA/SFAツールを導入し、使いこなすこと」という「手段」そのものにすり替わっていました。
「顧客接点を強化する」という本来の目的を、
- 「誰の(ターゲット顧客)」
- 「どのような課題を(顧客インサイト)」
- 「どのように解決し(提供価値)」
- 「その結果、ビジネスにどのようなインパクト(KPI)をもたらすのか」
といった、具体的なレベルまで掘り下げ、全社で共有するプロセスが、完全に欠落していたのです。目的が曖昧なままでは、現場の従業員は「なぜ、この面倒な作業をしなければならないのか」という問いに納得できず、変革の当事者にはなれません。
1-2. 教訓1:DXは「手段(How)」ではなく「目的(Why/What)」から始めよ
DXの第一歩は、最新のテクノロジーを調べることではありません。自社のビジネスと顧客を深く見つめ直し、「我々は何者で、どこへ向かおうとしているのか」という、企業の存在意義(パーパス)やビジョンにまで立ち返り、DXを通じて「何を成し遂げたいのか」を定義することです。
【図解】DXの失敗パターン vs 成功パターン
| 観点 | 失敗するDX(手段から始める) | 成功するDX(目的から始める) |
|---|---|---|
| 出発点 | 最新のAIツールを導入したい | 3年後、顧客に「究極のパーソナル体験」を提供したい |
| 思考の順序 | ツール(How)→ 目的(Why/What) | 目的(Why/What)→ 戦略 → 手段(How) |
| 議論の中心 | ツールの機能、価格、導入スケジュール | 顧客の課題、あるべき業務プロセス、測定すべき成果 |
| 現場の反応 | 「やらされ感」が強く、抵抗勢力となる | 「自分たちの未来のため」と、当事者意識が芽生える |
経営者は、テクノロジーの専門家である必要はありません。しかし、「DXによって、会社と顧客の未来をどう変えたいのか」という、揺るぎない「物語」を語る、最高のストーリーテラーでなければならないのです。
2. 失敗事例②「丸投げIT部門」- 経営と現場の“深い溝”
【ケーススタディ:中堅部品メーカーB社の物語】
B社の経営陣は、サプライチェーン全体の効率化を目指し、「全社の基幹システムを刷新する」という大規模なDXプロジェクトを立ち上げました。経営会議で高らかに宣言した後、社長は情報システム部長を呼び、「あとはよろしく頼む」と、プロジェクトの実行を完全に丸投げしてしまいました。
情報システム部門は、各事業部門にヒアリングを重ね、巨大な要件定義書を作成。外部のSIerと共に、2年がかりで新システムの開発を進めました。しかし、完成したシステムをいざ導入しようとすると、現場の各部門から「こんな機能は使えない」「我々の業務の実態と合っていない」という不満が噴出。結局、新システムはほとんど使われず、現場は旧システムを使い続けるという、最悪の事態に陥りました。
2-1. なぜ失敗したのか?「他人事」になった事業部門
この悲劇の原因は、DXの推進役を、情報システム部門という「他人」に丸投げしてしまったことにあります。
本来、業務プロセスを最も深く理解し、その変革の主役となるべきなのは、日々その業務を行っている「事業部門」のはずです。しかし、B社では、DXが「情報システム部門がやる、ITプロジェクト」と位置付けられてしまったため、事業部門は「お客様」として、ただ要望を伝えるだけの受け身の姿勢に終始してしまいました。
自分たちで変革の汗をかいていないため、プロジェクトへの当事者意識は皆無です。結果として、開発の途中で生じる細かな仕様の確認や、変化するビジネス環境への対応が疎かになり、最終的に出来上がったものは、誰の課題も解決しない「誰も望まなかったシステム」となってしまったのです。
2-2. 教訓2:DXの主語は、常に「事業部門」である
情報システム部門は、あくまでDXを技術で支える「パートナー」であり「支援者」です。DXプロジェクトを力強く牽引するエンジンは、その変革によって直接的な価値を生み出す、事業部門自身でなければなりません。
【図解】DX推進体制の失敗パターン vs 成功パターン
| 観点 | 失敗する推進体制 | 成功する推進体制 |
|---|---|---|
| プロジェクトオーナー | 情報システム部長 | 事業部門の責任者(役員・部長クラス) |
| 事業部門の役割 | 要件を伝える「お客様」 | 変革をリードする「主役」「オーナー」 |
| 情報システム部門の役割 | 要件を実現する「下請け」 | 技術で事業部門を支援する「パートナー」 |
| コミュニケーション | 要件定義書越しの、一方通行 | 日々対話を重ね、共に創り上げる「協創」 |
経営者は、DXプロジェクトの責任者に、情報システム部門の人間ではなく、最も変革への情熱とリーダーシップを持った、事業部門のエースを任命すべきです。そして、そのリーダーに、部門の壁を越えて全社を動かすための、十分な権限と予算を与えるという、明確なコミットメントが不可欠なのです。
3. 失敗事例③「サイロ化した組織」- “部分最適”の集合体がDXを阻む
【ケーススタディ:大手金融機関C社の物語】
C社では、全社的なDX推進の一環として、各部門がそれぞれ独自のデジタル化プロジェクトを進めていました。マーケティング部は、最新のMAツールを導入してリード獲得の効率化を。営業部は、SFAを導入して営業活動の可視化を。カスタマーサポート部は、FAQチャットボットを導入して問い合わせ対応の自動化を目指しました。
しかし、これらのプロジェクトは、完全に部門内で閉じており、部門間の連携は一切ありませんでした。その結果、マーケティング部が獲得したリード情報が、営業部のSFAにスムーズに連携されず、貴重な商談機会を逃す事態が発生。顧客は、Webサイトで伝えた内容を、営業担当者やサポート担当者に、何度も繰り返し説明させられるという、最悪の顧客体験を強いられました。
3-1. なぜ失敗したのか?「全体の価値」という視点の欠如
C社の失敗は、組織の「サイロ化(部門間の縦割り)」が原因です。各部門は、自分たちの業務効率化(部分最適)には熱心でしたが、その取り組みが、会社全体として、そして何よりも顧客にとっての「一貫した価値(全体最適)」にどう繋がるか、という視点が完全に欠落していました。
顧客は、企業の部門構造など知る由もありません。彼らにとって、企業との接点は、マーケティング、営業、サポートの全てを含んだ、一つの連続した「体験(カスタマージャーニー)」です。このジャーニーが、部門間の壁によって分断され、情報がスムーズに流れないことで、顧客満足度は著しく低下します。
DXの目的は、個別の業務をデジタル化することではなく、これらのサイロを打ち壊し、データを組織横断で連携させることで、シームレスで優れた顧客体験を創造することにあるのです。
3-2. 教訓3:組織の壁を壊し、部門横断の体制を築け
真のDXを実現するためには、従来の機能別組織(縦割り組織)の論理を超えた、部門横断のプロジェクト推進体制が不可欠です。
【図解】DXのための組織構造変革
- Before:サイロ型組織
- マーケティング部 ⇔ 営業部 ⇔ サポート部 ⇔ 開発部 (壁が存在)
- 特徴:
- コミュニケーションは、部門長経由の伝言ゲーム。
- データは、各部門のExcelやシステムに散在し、分断。
- 評価は、部門ごとのKPI。他部門への貢献は評価されない。
- 結果: 部分最適の追求、顧客体験の分断。
- After:クロスファンクショナルチーム
- 1つのチームに マーケター、営業、サポート、開発者、デザイナーが集結。
- 特徴:
- 共通の目標(例:顧客LTVの向上)を持つ。
- 日々、顔を合わせて直接コミュニケーション。
- データは、チーム共通のダッシュボードで一元的に可視化。
- 評価は、チームとしての成果。
- 結果: 全体最適の追求、シームレスな顧客体験の実現。
このようなチームを組成するには、各部門からエース級の人材を引き抜き、彼らが元の部門の論理に縛られずに活動できるような、強力な権限委譲が必要です。これは、既存の組織構造にメスを入れる、痛みを伴う改革ですが、この壁を乗り越えずして、DXの成功はあり得ません。
4. 失敗事例④「壮大すぎる計画」- 完璧な地図が遭難を招く
【ケーススタディ:総合商社D社の物語】
D社は、全く新しい分野での新規事業創出を目指し、DXを活用したプラットフォームビジネスの立ち上げを決定しました。プロジェクトチームは、数ヶ月をかけて、綿密な市場調査と競合分析を行い、想定される全ての機能を盛り込んだ、数百ページに及ぶ、完璧な「事業計画書」と「要件定義書」を作成しました。
その壮大な計画に基づき、開発はスタート。しかし、2年という長い開発期間の間に、市場のトレンドは変わり、強力な競合サービスが次々と出現。ようやく完成したプラットフォームは、リリースした時には、もはや誰のニーズも満たさない、時代遅れのサービスとなっていました。完璧なはずの地図は、チームを成功ではなく、遭難へと導いたのです。
4-1. なぜ失敗したのか?「ウォーターフォール型」の思考
D社の失敗原因は、不確実性の高い新規事業開発において、伝統的な「ウォーターフォール型」のアプローチを取ってしまったことにあります。
ウォーターフォール型とは、最初に全ての計画を完璧に固め、その計画通りに、後戻りせず開発を進めていく手法です。これは、仕様が明確で、変化の少ないプロジェクトには有効ですが、DXのような「正解が分からない」領域では、致命的な弱点を抱えています。
- 仮説の検証が遅すぎる: 最初の計画(仮説)が正しかったかどうかは、全ての開発が終わった、数年後にしか分かりません。その時点で間違いに気づいても、もはや手遅れです。
- 変化に対応できない: 開発の途中で、市場や顧客のニーズが変化しても、一度固めた計画を柔軟に変更することは極めて困難です。
4-2. 教訓4:小さく始め、素早く学び、アジャイルに適応せよ
不確実性の高いDXプロジェクトを成功に導く鍵は、「完璧な計画」ではなく、「高速な学習サイクル」です。この考え方を実践するためのアプローチが、「アジャイル開発」や「リーンスタートアップ」です。
【図解】開発アプローチの比較
| 観点 | ウォーターフォール | アジャイル |
|---|---|---|
| 計画 | 最初に全てを計画する(予測型) | 計画は変化することを前提とする(適応型) |
| 開発 | 大きな塊で、一度に全てを開発する | 小さな機能単位で、反復的に開発する |
| リリース | 全てが完成してから、一度だけリリース | 価値ある機能から、頻繁にリリース |
| 学習 | プロジェクトの最後に、一度だけ学ぶ | 短いサイクル(1〜4週間)で、常に学び続ける |
| リスク | 最後に大きなリスクが発覚する | 早期に小さなリスクを発見し、修正できる |
DXプロジェクトでは、最初から壮大な完成図を描く必要はありません。まずは、顧客の最も本質的な課題を解決できる、最小限の機能を持った製品(MVP: Minimum Viable Product)を、最短期間で作り上げ、市場に投入します。そして、実際のユーザーからのフィードバックという、最も価値のある「データ」を得て、学び、素早く改善していく。この「構築→計測→学習」のサイクルを、いかに速く回せるかが、成功と失敗を分けるのです。
5. 失敗事例⑤「変われない中間管理職」- “抵抗勢力”が変革を蝕む
【ケーススタディ:製造業E社の物語】
E社の経営トップは、DXによる抜本的な業務改革を掲げ、ボトムアップでのアイデア創出を奨励しました。若手社員たちは、これに応え、部門の壁を越えた有志チームを結成。データの活用による生産性向上のための、画期的なアイデアを提案しました。
しかし、その提案は、各部門の中間管理職(課長・部長クラス)の壁に阻まれてしまいます。「前例がない」「失敗したら誰が責任を取るんだ」「そんなことより、目の前の目標を達成しろ」。彼らは、変化に伴うリスクや、自身が築き上げてきた既存の業務プロセスが否定されることを恐れ、若手の挑戦的なアイデアをことごとく握り潰してしまいました。結果、若手社員のモチベーションは著しく低下し、DXの掛け声は、いつしか社内から聞こえなくなりました。
5-1. なぜ失敗したのか?ミドルマネジメントのジレンマ
この失敗の本質は、中間管理職が、DXにおける「推進役」ではなく、「最大の抵抗勢力」になってしまったことにあります。これは、彼らが無能だからではありません。むしろ、既存の体制の中で、真面目に、そして優秀に働いてきたからこそ、変化を受け入れられないという、根深いジレンマがあるのです。
- 成功体験への固執: 彼らは、これまでのやり方で成果を出し、評価されてきました。その成功体験が、新しいやり方への変化に対する、無意識の抵抗を生みます。
- 権限や役割の喪失への恐怖: DXによって業務が可視化・自動化されると、これまで彼らが担ってきた、情報のハブとしての役割や、部下を管理・統制するという権限が、失われるのではないかという恐怖を感じます。
- 評価制度の問題: 短期的な業績目標の達成で評価される彼らにとって、すぐに成果が出るか分からない、不確実なDXへの挑戦は、自らの評価を下げるリスクでしかありません。
5-2. 教訓5:DXの成否は、ミドルマネジメントの変革にかかっている
経営トップがどれだけ崇高なビジョンを語り、若手社員がどれだけ優れたアイデアを出しても、組織の中間層であるミドルマネジメントが動かなければ、変革は絵に描いた餅で終わります。彼らを「抵抗勢力」から「変革のキーパーソン」へと変えることこそ、経営者が最も注力すべき課題です。
【図解】ミドルマネジメントの役割変革(ビフォーアフター)
| 観点 | Before(旧来の管理者) | After(DX時代のサーバント・リーダー) |
|---|---|---|
| 主な役割 | 部下の管理、監督、指示命令 | 部下の支援、コーチング、障害物の除去 |
| 情報 | 情報を独占し、権力の源泉とする | 情報をオープンにし、チームの透明性を高める |
| 失敗への態度 | 失敗を追求し、責任を問う | 失敗を学習の機会と捉え、挑戦を奨励する |
| 評価の軸 | 個人の成果、短期的な目標達成 | チームの成果、長期的な価値創造への貢献 |
この役割変革を促すためには、彼ら自身が、新しいリーダーシップや、アジャイル開発、コーチングといったスキルを学ぶための、体系的なリスキリングの機会を提供することが不可欠です。そして、短期的な業績だけでなく、変革への挑戦そのものを評価する、新しい評価制度の導入も必要でしょう。ミドルマネジメントの変革は、DXにおける、最も困難で、しかし最も重要なレバレッジポイントなのです。
6. 失敗事例⑥「デジタル人材の不在」- “黒船”に乗る船乗りがいない
【ケーススタディ:地方銀行F社の物語】
F社は、地域経済のデジタル化に対応するため、フィンテックを活用した新しい金融サービスの開発を決定しました。経営陣は、外部の大手コンサルティングファームとSIerにプロジェクトを全面的に委託。彼らの助言通りに、最新のクラウド基盤と、AIを活用した審査モデルを導入しました。
プロジェクトは、計画通りに完了し、華々しくサービスはリリースされました。しかし、問題はその後でした。運用・保守を任された行内のIT部門には、クラウドやAIを扱える人材が一人もおらず、小さな不具合の修正や、顧客の要望に応じた機能改善が、全く行えません。結局、サービスはリリースされた時点から全く進化できず、ユーザーは徐々に離れ、プロジェクトは塩漬け状態となってしまいました。
6-1. なぜ失敗したのか?「内製化」という視点の欠如
F社の失敗は、DXを推進するための最も重要な資産である「人材」を、外部からの購入(アウトソーシング)で済ませようとしてしまったことに起因します。
コンサルタントやSIerは、一時的に高度な知識やリソースを提供してくれますが、彼らはいずれ去っていきます。プロジェクトが終わった後、自社の組織の中に、新しい技術を理解し、改善し続けられる能力(ケイパビリティ)が何も残っていなければ、そのDXは持続可能なものにはなりません。
車に例えるなら、F社は、最新鋭のF1マシンを大金で買ったものの、そのマシンを運転し、セッティングし、修理できるドライバーもメカニックも、自社で一人も育てていなかったのです。これでは、レースで走り続けることなど、到底不可能です。
6-2. 教訓6:外部委託に頼らず、社内の人材を育成(リスキリング)せよ
DXの真の成功とは、単に新しいシステムを導入することではありません。そのプロセスを通じて、組織の「人材」が変革し、デジタル時代に対応できる新しい能力を身につけること、すなわち「組織能力の変革」そのものです。
【図解】DXにおける人材戦略の比較
| 観点 | 失敗する人材戦略(アウトソース依存型) | 成功する人材戦略(内製化・育成型) |
|---|---|---|
| 基本思想 | デジタルは専門家の仕事。餅は餅屋に。 | デジタル能力は、自社の競争力の源泉である。 |
| 人材獲得 | 外部のコンサルやSIerに「丸投げ」する。 | 社内のポテンシャル人材を「リスキリング」する。 |
| ナレッジ | プロジェクト終了と共に、社外に流出する。 | 成功も失敗も、全てが組織の資産として蓄積される。 |
| スピード | 小さな改善でも、外部への発注が必要で遅い。 | 内製のチームが、迅速かつ柔軟に改善を続けられる。 |
もちろん、全ての機能を内製化する必要はありません。外部の専門家の力を戦略的に活用することは重要です。しかし、少なくとも、DXの中核となる領域においては、自社のビジネスを深く理解した、社内の人材が主導権を握るべきです。
そのためには、経営者が、従業員のスキルアップとリスキリングを、単なるコストではなく、未来への最も重要な「投資」と位置づけ、体系的な教育プログラムや、挑戦の機会を提供することが不可欠です。デジタルスキルを身につけた人材が、社内で正当に評価され、魅力的なキャリアアップの道筋を描けるようにすること。それが、優秀な人材を惹きつけ、定着させるための唯一の道です。この分野での経験は、個人の転職市場における価値も大きく高めます。
7. 失敗事例⑦「顧客不在のDX」- 独りよがりの“カイゼン”
【ケーススタディ:運輸会社G社の物語】
G社では、長年の課題であった、ドライバーの非効率な配送ルート計画を改善するため、AIを活用した「最適ルート検索システム」を開発しました。システムは、過去の走行データや交通状況を分析し、理論上、最も効率的なルートを算出。経営陣は、これにより、燃料費の大幅な削減と、配送時間の短縮が実現できると、大きな期待を寄せていました。
しかし、現場のドライバーたちからは、不満の声が相次ぎました。「この道は、データ上は近いけど、実際は道が狭くて大型トラックでは通れない」「この時間帯は、ベテランなら、渋滞を避ける裏道を知っている」。システムは、現場の暗黙知や、数値化できないリアルな状況を全く考慮しておらず、かえって非効率なルートを提示することも少なくありませんでした。結局、ドライバーたちは、誰もそのシステムを使わなくなりました。
7-1. なぜ失敗したのか?「現場」と「顧客」という視点の欠如
G社のDXは、技術的には高度であったかもしれませんが、その変革の中心にいるはずの「人間」、すなわち、実際にそのシステムを使う「現場の従業員(社内顧客)」と、その先にいる「エンドユーザー(社外顧客)」の視点が、完全に抜け落ちていました。
- 現場の無視: 経営層と開発者は、現場のドライバーたちが長年培ってきた、貴重な経験や知恵(暗黙知)に敬意を払わず、彼らを単なる「オペレーター」として扱ってしまいました。変革のプロセスに現場を巻き込まず、トップダウンで「正しい答え」を押し付けたことが、彼らのプライドを傷つけ、強い抵抗感を生んだのです。
- 顧客価値の不在: そもそも、「配送ルートの最適化」は、あくまで企業側の効率化(コスト削減)が主目的です。それが、最終的に「荷物がより早く、より確実に届く」といった、顧客にとっての価値向上にどう繋がるのか、という視点が希薄でした。
7-2. 教訓7:全ての変革は、顧客価値の向上から逆算せよ
DXは、社内向けの業務改善(Internal DX)と、社外向けの顧客価値創造(External DX)の両輪で進める必要がありますが、その最終的な目的は、常に「顧客価値の最大化」でなければなりません。
【図解】DXの2つの側面と最終ゴール
[業務改善 (Internal DX)]
- 例:RPAによる事務作業の自動化、SFAによる営業活動の効率化
- 目的:コスト削減、生産性向上
↓
[顧客価値の向上 (External DX)] - 例:ECサイトのパーソナライズ、アプリによる新しい顧客体験の提供
- 目的:売上向上、顧客満足度向上
↑ これら全ての活動の最終ゴールは…
★★★ 顧客ロイヤルティの最大化 ★★★
優れたDXとは、社内向けの業務改善が、最終的に、より良い製品やサービス、より迅速な対応といった形で、顧客価値の向上に結実しているものです。
そのためには、
- デザイン思考のアプローチ: 常に、システムを使うユーザー(従業員や顧客)に共感し、彼らの視点に立って、課題を発見し、解決策を共に創り上げていく。
- Webマーケティングの知見活用: Webマーケティングで用いられる、カスタマージャーニーマップの作成や、A/Bテストといった手法は、顧客理解を深め、仮説を検証する上で、DXプロジェクト全体に応用できる強力なツールです。
「我々のDXは、本当に顧客を幸せにしているか?」この問いを、常に自問自答し続けること。それこそが、独りよがりの改善で終わらない、真に価値ある変革への道標となります。
まとめ:失敗の地図を手に、成功への航海へ出発しよう
本記事では、DX推進の航海で多くの企業が陥りがちな、7つの暗礁(失敗事例)と、そこから得られる、安全な航路を示す海図(教訓)について解説してきました。
最後に、7つの教訓を、あなたのDXプロジェクトを点検するためのチェックリストとして、改めて整理します。
- 【教訓1】DXの目的は明確か?
ツール導入という「手段」が目的化していないか。DXで「何を」成し遂げたいのかという物語を、経営者自身の言葉で語れているか。 - 【教訓2】DXの主役は誰か?
情報システム部門に「丸投げ」していないか。事業部門が、当事者としてプロジェクトを牽引する体制になっているか。 - 【教訓3】組織の壁は壊せているか?
部門最適に陥っていないか。顧客への一貫した価値提供のために、部門横断のチームが機能しているか。 - 【教訓4】アジャイルな進め方か?
完璧で壮大な計画に固執していないか。「小さく始め、素早く学び、柔軟に適応する」サイクルを回せているか。 - 【教訓5】中間管理職は変革の仲間か?
ミドルマネジメントが「抵抗勢力」になっていないか。彼らを「変革のキーパーソン」に変えるための支援とリスキリングを行っているか。 - 【教訓6】デジタル人材は社内にいるか?
外部委託に依存しすぎていないか。自社の競争力の源泉となるデジタル能力を、社内で育成する覚悟と投資があるか。 - 【教訓7】そのDXは、顧客を向いているか?
企業側の論理による、独りよがりの改善になっていないか。全ての活動が、最終的な「顧客価値の最大化」に繋がっているか。
DXの旅は、決して平坦な道のりではありません。しかし、先人たちの失敗という貴重な地図を手にすれば、致命的な遭難を避け、成功という目的地にたどり着く確率は、格段に高まります。
この記事が、あなたの会社のDXという航海の、信頼できる羅針盤となることを、心から願っています。