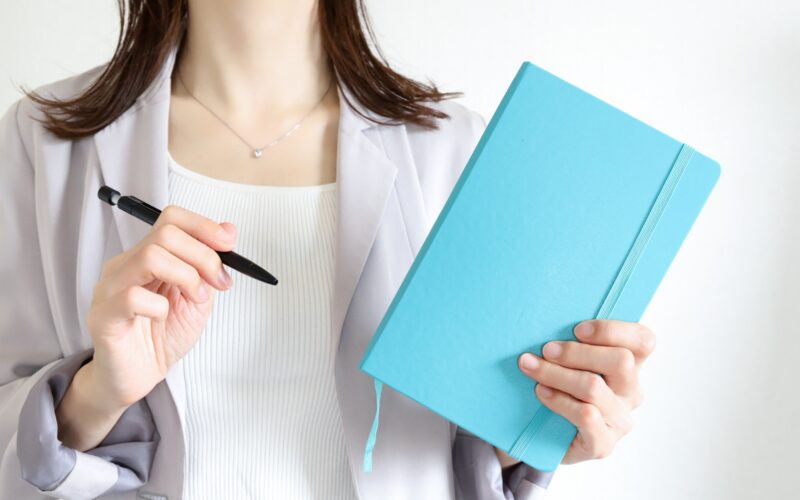はじめに:あなたの顧客は「店舗派」か「EC派」か?その“二者択一”が、ビジネスを失速させる
「実店舗の売上は、ECの台頭で、年々減少している…」
「ECの、新規顧客獲得コストは、高騰し続け、利益を圧迫している…」
「店舗とECで、顧客情報も、在庫も、バラバラ。まるで、別の会社のように、運営されている…」
もし、あなたが、小売・EC業界の、ビジネスリーダーや、マーケターとして、このような課題に、頭を悩ませているとしたら、その根本的な原因は、顧客を「店舗で買う人」と「ECで買う人」というように、分断して捉えてしまっていることにあるのかもしれません。
現代の、賢い消費者は、もはや、オンラインと、オフラインの垣根を、意識していません。
- スマートフォンで、商品の口コミを、徹底的に調べてから、実店舗に、足を運び、実物を確認する(ウェブルーミング)。
- 実店舗で、商品を手に取り、店員から、詳しい説明を受けた後、結局、最も価格が安い、ECサイトで購入する(ショールーミング)。
- ECサイトで、注文した商品を、近所の店舗で、受け取り、ついでに、別の商品も買っていく(クリック&コレクト)。
このように、顧客は、オンラインと、オフラインの、それぞれの「良いとこ取り」をしながら、二つの世界を、自由自在に、行き来しています。
この、新しい顧客行動が、当たり前になった時代において、企業が、顧客から選ばれ続けるための、唯一の、そして、最強の戦略。それが、「OMO (Online Merges with Offline)」です。
この記事は、「OMOという言葉は知っているが、具体的に、何をすれば良いのか、分からない」「どうすれば、店舗とECの、連携を、深められるのか」と模索している、すべての小売・EC業界の、関係者のために書かれました。
本記事を読み終える頃には、あなたは以下のものを手にしているはずです。
- OMOが、単なる、マーケティングの、バズワードではない、その本質的な、戦略的価値の理解
- 店舗とECの、壁を溶かす、具体的なテクノロジーと、先進的な、活用事例
- OMOの、究極的なゴールである「パーソナライズされた、顧客体験」の、実現方法
- そして、この、OMO時代を、生き抜くために、求められるスキルと、未来のキャリアアップや転職に繋がる、明確なキャリアビジョン
OMOは、単なる、チャネル戦略では、ありません。それは、顧客理解の、あり方を、根底から変革し、ビジネスの、全ての活動を、顧客中心に、再構築する、経営改革そのものです。この変革を、リードする経験は、最高のリスキリングであり、スキルアップの機会となります。
さあ、店舗とECの、間に存在する、見えない壁を、打ち壊す、旅を、ここから始めましょう。
1. OMOとは何か?マルチチャネル、オムニチャネルとの、決定的な違い
OMO(オーエムオー)を、正しく理解するためには、まず、それ以前の、リテール戦略の、進化の歴史を、知っておくことが、近道です。
多くの企業が、OMOを目指す過程で、「マルチチャネル」「オムニチャネル」という、段階を、経てきました。
1-1. マルチチャネル:チャネルが「点」として、存在する段階
- コンセプト:
- 企業が、顧客との接点として、複数のチャネル(店舗、ECサイト、カタログ通販など)を、それぞれ「独立」して、運営している状態。
- 特徴:
- 各チャネルは、サイロ化(分断)しており、顧客情報や、在庫情報も、バラバラに管理されている。
- 顧客は、利用したいチャネルを、選ぶことはできるが、チャネルを、またいだ、一貫したサービスを、受けることはできない。
- 例:
- 店舗の、ポイントカードは、ECサイトでは使えない。
- ECサイトで、見た商品の在庫が、近所の店舗にあるか、分からない。
1-2. オムニチャネル:「点」が「線」で、繋がり始める段階
- コンセプト:
- 複数のチャネルを、連携させ、顧客に、一貫性のある、購買体験を提供しようとする戦略。
- 特徴:
- 顧客情報や、在庫情報が、チャネル間で、連携・統合される。
- 顧客は、チャネルの、境界線を、意識することなく、スムーズに、サービスを、利用できる。
- 例:
- ECサイトで注文した商品を、店舗で受け取れる(クリック&コレクト)。
- 店舗で、欠品している商品を、その場で、ECサイトから注文し、自宅に配送してもらう。
- 店舗とECで、共通のポイントプログラムを、利用できる。
1-3. OMO (Online Merges with Offline):「線」が溶け合い、一つの「円」になる段階
- コンセプト:
- オムニチャネルを、さらに進化させ、もはや、オンラインと、オフラインを、区別する、という発想そのものを、なくし、両者が、完全に融合した、一つの、シームレスな顧客体験を、提供する戦略。
- 主語の違い:
- オムニチャネルの主語は「企業」でした。「企業が、いかにして、チャネルを連携させるか」という、視点です。
- OMOの主語は「顧客」です。「顧客にとって、オンラインか、オフラインかは、関係ない。あるのは、そのブランドとの、ただ一つの、連続した体験だけだ」という、視点です。
- OMOの、核心:データの完全統合
- OMOの、最も重要な、本質は、オンラインでの、顧客の行動データ(閲覧履歴、クリック履歴など)と、オフライン(店舗)での、顧客の行動データ(来店履歴、購買履歴、店内での動きなど)を、完全に統合し、一人の顧客の、360度の、解像度の高い、デジタルな人格(ID)として、捉えることにあります。
- 例:
- 店舗に来店した、顧客のスマートフォンアプリに、その顧客が、過去にECサイトで、閲覧していた商品に基づいた、パーソナライズされた、クーポンが、配信される。
- 店舗の、サイネージ広告が、目の前に立った、顧客の属性(推定)に応じて、表示内容を、リアルタイムで、変化させる。
OMOは、全ての顧客接点を、データ取得の、センサーと位置づけ、そのデータを、活用して、究極の、パーソナライゼーションを、実現しようとする、データドリブン戦略の、究極の姿なのです。
2. なぜ今、OMOが、小売・EC業界の、未来を左右するのか?
OMOは、単なる、先進的な、マーケティング手法では、ありません。それは、変化の激しい、現代の市場で、小売・EC企業が、生き残り、成長し続けるための、「生存戦略」そのものと、言えます。
2-1. 顧客行動の、不可逆な変化への対応
前述の通り、現代の顧客は、オンラインと、オフラインを、当たり前のように、行き来します。
この、「ハイブリッドな、購買行動」に、対応できない企業は、顧客の、複雑なニーズを、満たすことができず、徐々に、顧客を失っていきます。
- ショールーミング対策:
- 店舗で、商品の説明だけを聞いて、ECで買ってしまう、顧客を、嘆くのではなく、店舗での、優れた接客体験を、フックに、その場で、自社のECサイトへ誘導し、オンライン限定の、特典を提示する、といった、対策が可能になります。
- ウェブルーミングの、機会最大化:
- オンラインで、下調べをしてから、来店する、意欲の高い顧客に対して、ECサイト上で、「この商品は、〇〇店に、在庫があります」と、リアルタイムの、在庫情報を提示し、スムーズな、来店を促すことができます。
OMOは、オンラインと、オフラインを、競合関係として、捉えるのではなく、互いの強みを、活かし合う、補完関係として、再構築する、発想の転換なのです。
2-2. ECと、実店舗、それぞれの「限界」の、突破
- ECの限界:高騰する、顧客獲得コスト (CAC)
- EC市場の、競争が激化する中で、Web広告などを、通じた、新規顧客の獲得コスト(CAC)は、年々、高騰し続けています。
- 実店舗は、その地域における、強力な「顧客接点」であり、「ショールーム」であり、そして、「ブランド体験の場」として、オンラインの、顧客獲得を、補完する、重要な役割を、担います。
- 実店舗の限界:地理的な、制約と、データ取得の困難さ
- 実店舗は、商圏が、地理的に限定され、また、「誰が、いつ、何に興味を持ったが、買わなかったか」といった、購買に至らない、行動データを、取得することが、困難でした。
- OMOは、店舗を、オンラインへの「送客装置」として、機能させ、また、アプリなどを通じて、オフラインの行動を、データ化することで、これらの限界を、突破します。
2-3. データの力で、LTV(顧客生涯価値)を、最大化する
OMO戦略の、究極的なゴールは、LTV (Life Time Value / 顧客生涯価値) の、最大化です。
OMOによって、オンラインと、オフラインの、両方の、顧客データが、統合されることで、
- 顧客解像度の、飛躍的な向上:
- 「この顧客は、オンラインでは、Aという商品を、よく見ているが、店舗では、Bという商品を、購入している」といった、これまで、見えなかった、顧客の、多面的な、インサイトを、得ることができます。
- 究極の、パーソナライゼーション:
- この、深い顧客理解に基づいて、一人ひとりの、顧客に対して、最適な、コミュニケーション(商品の推薦、クーポンの発行など)を、最適なチャネル(アプリ、メール、店舗のサイネージなど)で、提供することが可能になります。
- 顧客ロイヤルティの、醸成:
- 「このブランドは、本当に、私のことを、よく分かってくれている」という、感動的な、顧客体験(CX)は、価格競争を、超えた、強い、顧客ロイヤルティを育み、顧客が、長期にわたって、自社のファンであり続けてくれる、強力な、理由となります。
この、LTVを、最大化する、データドリブンな、アプローチこそが、OMOが、もたらす、最大の、経営インパクトなのです。
3. OMOの、心臓部|「統合ID」と「CDP」という、技術基盤
OMOという、壮大なビジョンを、実現するためには、その、土台となる、技術的な「心臓部」が、不可欠です。
それが、「統合ID」と、「CDP (カスタマーデータプラットフォーム)」です。
これらがなければ、OMOは、単なる、掛け声倒れに、終わってしまいます。
3-1. 統合ID:バラバラの「顧客」を、一人の「あなた」へ
- 課題:
- 多くの企業では、オンライン(ECサイト)の顧客と、オフライン(店舗)の顧客が、別々のIDで、管理されています。
- ECサイトの、会員Aさんと、店舗の、ポイントカードを持つ、鈴木様が、同一人物であるということを、システムが、認識できていないのです。
- これでは、オンラインと、オフラインの、行動データを、統合することは、不可能です。
- 解決策(統合ID):
- 役割:
オンラインと、オフラインの、顧客IDを、名寄せし、統合することで、「一人の顧客」として、認識するための、仕組みです。 - 実現方法:
- 店舗での、アプリ会員証の、提示:
最も、一般的な方法です。顧客に、公式スマートフォンアプリを、ダウンロードしてもらい、店舗での、会計時に、アプリの会員証(バーコードなど)を、提示してもらう。 - 会員カードと、ECアカウントの、連携:
既存の、ポイントカードの会員情報と、ECサイトの会員情報を、Webサイト上で、顧客自身に、紐づけてもらう。
- 店舗での、アプリ会員証の、提示:
- 役割:
この「統合ID」の、普及率こそが、あなたの会社の、OMO戦略の、成否を分ける、最初の、そして、最も重要なKPIとなります。
3-2. CDP (Customer Data Platform)|OMOの「司令塔」となる、顧客データの脳
統合IDによって、顧客が「一人」として、認識できるようになったら、次なるステップは、その顧客に関する、あらゆるデータを、集約・統合・活用するための「司令塔」を、構築することです。
その役割を、担うのが、CDP (カスタマーデータプラットフォーム)です。
- CDPの、4つのコア機能:
- ① データの「収集 (Collect)」:
- オンラインのデータ(Webサイトの閲覧履歴、ECでの購買履歴、アプリの利用履歴など)
- オフラインのデータ(店舗のPOSデータ、来店履歴、コールセンターへの問い合わせ履歴など)
- 外部のデータ(広告データ、天候データなど)
- といった、社内外に、散在する、あらゆる、顧客データを、リアルタイムで、収集します。
- ② データの「統合 (Unify)」:
- 収集した、バラバラのデータを、「統合ID」をキーとして、名寄せし、一人の顧客の、時系列の、行動履歴として、再構築します。
- これにより、「360度、顧客ビュー」と呼ばれる、顧客の、完全な、デジタルプロファイルが、生成されます。
- ③ データの「分析 (Analyze)」:
- 統合された、顧客プロファイルを、様々な切り口で、分析・セグメンテーションします。
- (例:「過去3ヶ月以内に、店舗とECの、両方で、購入があり、かつ、特定の商品カテゴリーを、よく閲覧している、優良顧客セグメント」)
- ④ データの「連携・活用 (Activate)」:
- 分析・セグメント化された、顧客リストを、MA(マーケティングオートメーション)、Webマーケティングの広告配信プラットフォーム、BIツール、店舗の接客ツールといった、様々な、外部のツール(施策実行ツール)に、連携します。
- ① データの「収集 (Collect)」:
CDPは、まさに、OMOの「脳」であり、「神経網」です。
この、強力なデータ基盤を、持つことで、企業は、次章で解説するような、高度な、パーソナライズ施策を、実現することが、可能になるのです。
CDPを、設計・運用できるスキルは、これからの、マーケターにとって、極めて市場価値の高い、専門性となり、キャリアアップに、直結します。
4. 【OMO実践編①】デジタルを「店舗」に持ち込む、新しい顧客体験
OMOの、技術的な基盤が、整ったら、いよいよ、それを、具体的な「顧客体験(CX)」へと、落とし込んでいきます。
まずは、オフラインである「店舗」での体験を、デジタルの力で、いかに、拡張できるか、その、具体的な戦略と、事例を見ていきましょう。
4-1. クリック&コレクト / BOPIS|ECと店舗の、最高の“出会いの場”
- コンセプト:
- クリック&コレクト (Click & Collect):
ECサイトで、注文した商品を、顧客が、指定した、最寄りの店舗で、受け取ることができるサービス。 - BOPIS (Buy Online Pick-up In Store):
ほぼ、同義で使われます。
- クリック&コレクト (Click & Collect):
- 顧客にとっての、メリット:
- 送料が、無料になる。
- 宅配便を、待つ必要がなく、自分の、好きなタイミングで、商品を受け取れる。
- もし、サイズが合わなかったり、イメージと違ったりした場合、その場で、返品・交換ができる、安心感。
- 企業にとっての、メリット:
- 「ついで買い(クロスセル)」の、誘発:
商品を受け取りに、来店した顧客が、店内の、他の商品にも、目を向け、追加の購入に繋がる、可能性が、非常に高い。 - ECの、弱点である「配送コスト(ラストワンマイル問題)」を、削減できる。
- 店舗を、ECの「物流拠点」として、活用できる。
- 「ついで買い(クロスセル)」の、誘発:
- 先進事例:
- ユニクロや、ヨドバシカメラなどが、早くから導入し、多くの顧客に、支持されています。
4-2. スマートフォンアプリが、最強の「接客ツール」になる
OMO戦略において、顧客のスマートフォンアプリは、単なる、ECの入り口では、ありません。
それは、店舗での、顧客体験を、パーソナライズするための、最強の「リモコン」であり、「接客ツール」となります。
- チェックイン機能と、パーソナライズ・クーポン:
- 来店した顧客が、アプリで、チェックインすると、その顧客の、過去の購買履歴や、ECサイトでの、閲覧履歴に基づいて、「あなたへのおすすめ商品」や「本日限定の、特別クーポン」が、プッシュ通知で、配信される。
- 店内ナビゲーションと、ビーコン技術:
- 広大な、店舗の中で、顧客が探している、商品の場所まで、アプリが、ARなどで、道案内をしてくれる。
- 特定の、売り場に近づくと、ビーコン(近距離無線技術)が、それを検知し、その売り場の、関連商品の、お得情報を、自動で配信する。
- セルフスキャン・セルフ決済(レジレス):
- 顧客が、購入したい商品の、バーコードを、自分のスマホアプリで、スキャンし、そのまま、アプリ内で、決済を完了させる。
- これにより、レジに並ぶ、という、最大のストレスから、顧客を解放し、店舗側も、レジ業務の、省人化が、可能になります。
4-3. デジタルサイネージと、店舗のメディア化
- コンセプト:
- 店舗内に、設置された、デジタルサイネージ(電子看板)が、単なる、一方的な、広告表示装置から、顧客と、インタラクティブに、コミュニケーションする「メディア」へと、進化します。
- 活用例:
- インタラクティブ・サイネージ:
顧客が、サイネージの、タッチパネルを操作し、商品の、詳細情報や、コーディネート例、口コミなどを、その場で、確認できる。 - パーソナライズ・サイネージ:
サイネージに、搭載されたカメラが、目の前に立った、顧客の、年代や、性別を、AIが推定し、その、属性に合わせた、広告や、おすすめ商品を、リアルタイムで、表示する。 - 在庫情報との連携:
ECサイトの、売れ筋ランキングや、レビューを、店舗のサイネージに、リアルタイムで表示し、オンラインの「人気」を、オフラインの、購買意欲へと、繋げる。
- インタラクティブ・サイネージ:
これらの、施策は、店舗を、単に「商品を売る場所」から、データに基づいた、新しい「顧客体験を、創造する場所」へと、再発明するのです。
5. 【OMO実践編②】「店舗」の強みを、デジタルに活かす、新しいEC戦略
OMOは、逆の視点、すなわち、オンラインである「ECサイト」の体験を、いかにして、オフライン(店舗)の、強みを取り込んで、豊かにできるか、という、アプローチも、可能にします。
ECサイトが、単なる「自動販売機」ではなく、人間的な、温かみと、信頼感のある、接客の場へと、進化するのです。
5-1. ライブコマース:店舗が、テレビ局になる
- コンセプト:
- 店舗の、スタッフや、インフルエンサーが、ライブ動画配信を通じて、リアルタイムで、商品を、紹介・販売する、Eコマースの手法。
- 視聴者(顧客)は、チャット機能を通じて、リアルタイムで、質問をしたり、コメントをしたりでき、配信者と、双方向の、コミュニケーションを、楽しむことができます。
- もたらされる価値:
- 高い、コンバージョン率:
商品の、質感や、使い方を、動画で、リアルに伝えることができ、視聴者の、購買意欲を、強く刺激します。 - 顧客との、エンゲージメント強化:
ライブならではの、一体感や、臨場感が、ブランドへの、親近感や、エンゲージメントを、高めます。 - 店舗スタッフの、新しい活躍の場:
カリスマ的な、販売スキルを持つ、店舗スタッフが、地理的な制約を、超えて、全国の顧客に、アプローチできる、新しい「スター」となる、可能性があります。これは、彼らにとって、新しいスキルアップとキャリアアップの、機会となります。
- 高い、コンバージョン率:
5-2. オンライン接客(パーソナル・スタイリング)
- コンセプト:
- ECサイトを、閲覧している顧客が、「相談したい」と思った時に、ボタン一つで、店舗の、専門スタッフと、ビデオ通話を繋ぎ、一対一の、パーソナルな、接客を、受けられるサービス。
- もたらされる価値:
- 高単価商品の、EC化率向上:
アパレル、家具、宝飾品といった、購入の、意思決定に、専門的なアドバイスが、必要な、高単価商材の、オンラインでの、購買のハードルを、大きく下げます。 - 店舗の、アイドルタイムの有効活用:
店舗に、顧客がいない、空き時間(アイドルタイム)を、オンライン接客に、充てることで、店舗スタッフの、生産性を、向上させることができます。
- 高単価商品の、EC化率向上:
5-3. 店舗在庫の、ECサイトでの可視化と、活用
- コンセプト:
- ECサイト上で、「この商品は、あなたの、最寄りの〇〇店に、在庫が〇点あります」というように、店舗の、リアルタイム在庫情報を、表示し、顧客が、来店するか、ECで購入するかの、選択肢を、提供する。
- もたらされる価値:
- 機会損失の、防止:
ECサイトで、在庫切れでも、店舗に在庫があれば、顧客を、店舗へと誘導し、販売機会の損失を、防ぐことができます。 - 店舗からの、EC発送(店舗受け、店舗出荷):
ECの、注文に対して、EC専用の、物流倉庫からだけでなく、顧客の、最寄りの店舗から、商品を発送することで、配送時間を、短縮し、配送コストを、削減する。
これにより、店舗は、販売拠点であると同時に、ECの、ミニ物流拠点(ダークストア)としての、役割も、担うようになります。
- 機会損失の、防止:
これらの、施策は、ECサイトの、利便性と、店舗の、人間的な、温かみや、信頼感を、融合させ、「最高の、おもてなし」を、デジタル上で、実現するための、挑戦なのです。
6. OMOの、究極ゴール「パーソナライゼーション」が、もたらす顧客体験
OMO戦略の、様々な、実践例を、見てきました。そして、これらの、全ての施策が、最終的に、目指す、一つの、究極的なゴール。それが、「パーソナライゼーション」です。
パーソナライゼーションとは、統合された、顧客データを、基に、一人ひとりの、顧客の、興味・関心、購買履歴、そして、その時の、状況(コンテクスト)に合わせて、提供する、情報、商品、そして、体験の全てを、最適化することです。
6-1. データが、紡ぎ出す「個客」の、物語
OMOによって、統合された、360度、顧客ビューは、もはや、単なるデータの集合体では、ありません。それは、一人の「個客」の、ブランドとの、関わりの「物語(ジャーニー)」そのものです。
- 例:顧客Aさん(30代、女性、都内在住)の、物語
- [オンライン] Instagram広告で、新商品の、ワンピースを、認知。
- [オンライン] ECサイトで、そのワンピースの、詳細と、レビューを、3回閲覧。
- [オフライン] 週末、最寄りの、渋谷店に来店。(アプリの、チェックイン機能で、来店を検知)
- [オフライン] 店内で、そのワンピースを、試着するが、購入には至らず、退店。
- [オンライン] 翌日、Aさんの、スマートフォンに、「昨日、ご試着いただいた、ワンピースに、ぴったりの、カーディガンの、ご紹介」という、プッシュ通知が、届く。
- [オンライン] その、コーディネート提案が、気に入り、ECサイトで、ワンピースと、カーディガンの両方を、購入。受け取りは、会社の、最寄りである、新宿店を、指定(クリック&コレクト)。
6-2. 「予測」と「提案」による、新しい関係
この、深い顧客理解は、企業と、顧客の関係を、新しい次元へと、進化させます。
- 予測的レコメンデーション:
- 単に、過去に買ったものと、類似の商品を、推薦するだけでなく、AIが、顧客の、行動パターンから、「次に、欲しくなるであろう、商品」を、予測し、先回りして、提案する。
- コンテクスチュアル(文脈的)な、コミュニケーション:
- 顧客の、「今、いる場所」「今の時間」「今の天気」といった、リアルタイムの、文脈(コンテクスト)に合わせて、最適な情報を、提供する。
- 例:「雨が、降ってきましたね。本日、店舗で、お買い上げのお客様に、雨の日限定の、ポイント2倍クーポンを、プレゼントします」
- 顧客の、「今、いる場所」「今の時間」「今の天気」といった、リアルタイムの、文脈(コンテクスト)に合わせて、最適な情報を、提供する。
6-3. パーソナライゼーション時代の「Webマーケティング」
この、パーソナライゼーションの、実現は、Webマーケティングの、あり方を、大きく変えます。
- マス・マーケティングから、One to Oneマーケティングへ:
- 全ての顧客に、同じメッセージを、送る、マス広告の、効率は、低下し、一人ひとりに、最適化された、One to Oneの、アプローチが、主流となります。
- チャネル中心から、顧客中心へ:
- 「ECサイトの、CVRを、上げる」「店舗の、客単価を、上げる」といった、チャネルごとの、部分最適の、目標設定から、「顧客Aさんの、LTV(顧客生涯価値)を、最大化する」という、顧客を中心とした、全体最適の、目標設定へと、シフトします。
この、パーソナライゼーションを、実現するための、CDPの設計・運用、そして、データ分析のスキルは、これからの、マーケターにとって、最も、市場価値の高い、専門性となり、スキルアップと、キャリアアップを、約束するものです。
7. OMO時代に、求められる、新しい「小売のプロ」とは
OMOへの、移行は、小売・EC業界で働く、私たち、一人ひとりの、役割と、求められるスキルを、大きく、変えていきます。
これまで、評価されてきた、経験や、勘だけでは、生き残れない、時代が、到来したのです。
7-1. 店舗スタッフ:「販売員」から「ブランドの、体現者」へ
OMO時代の、店舗スタッフは、単に、商品を、レジで販売するだけの「販売員」では、ありません。
- 求められる、新しい役割:
- ブランドの、体現者(アンバサダー):
顧客と、直接、触れ合う、最も重要な、接点として、ブランドの、世界観や、物語を、情熱を持って、伝える。 - コミュニティ・ビルダー:
店舗を、地域の、顧客が集う、コミュニティの、ハブとして、機能させる。 - デジタルへの、案内人:
顧客に、スマートフォンアプリの、便利な使い方を、教えたり、オンライン接客で、全国の顧客と、繋がったりする。 - コンテンツ・クリエイター:
ライブコマースで、自らの、言葉で、商品の魅力を、発信する。
- ブランドの、体現者(アンバサダー):
これらの、新しい役割を、担うためには、接客スキルに加えて、デジタルツールを、使いこなす、リテラシーや、コンテンツを、発信する能力といった、新しいスキルアップが、不可欠となります。
7-2. EC担当者・マーケター:「サイト運営者」から「CXデザイナー」へ
OMO時代の、EC担当者や、マーケターは、単に、Webサイトの、更新や、広告運用を、行うだけの、存在では、ありません。
- 求められる、新しい役割:
- CX(顧客体験)デザイナー:
オンラインと、オフラインを、横断した、顧客の、ジャーニー全体を、設計し、全ての、タッチポイントで、最高の体験を、提供する、責任者。 - データアナリスト:
CDPに、蓄積された、膨大な、顧客データを、分析し、ビジネスに、繋がる、インサイトを発見する。 - テクノロジー・エバリュエーター:
MA, CDP, BIツールといった、多様な、マーケティング・テクノロジーを、理解し、自社の戦略に、最適なツールを、選定・導入できる。
- CX(顧客体験)デザイナー:
これらの、役割を、担うためには、従来の、Webマーケティングの、知識に加えて、データサイエンス、UXデザイン、そして、店舗オペレーションへの、深い理解といった、越境的な、リスキリングが、求められます。
7-3. OMOが拓く、新しいキャリアパスと、有利な転職
これらの、新しいスキルを身につけ、OMO戦略を、推進した経験は、あなたの、キャリアに、これまでにない、多様で、魅力的な、選択肢をもたらします。
- OMOストラテジスト / CXマネージャー:
- 企業の、OMO戦略、CX戦略全体を、統括する、専門職。
- リテールメディア責任者:
- 自社の、店舗や、ECサイトを、一つの「メディア」として、捉え、広告事業などの、新しい、収益源を、開発する。
- データアナリスト / グロースハッカー:
- 顧客データの、分析を、専門とし、サービスの成長(グロース)を、ミッションとする。
これらの、新しい職種は、現在、人材が、圧倒的に不足しており、高い専門性を、身につけることができれば、極めて、有利な条件での転職や、大幅なキャリアアップが、可能です。
OMOへの、挑戦は、あなたの、キャリアの、可能性を、無限に、広げる、新しい、フロンティアなのです。
8. まとめ:OMOは、顧客への「究極の、おもてなし」
本記事では、小売・EC業界の、DXの、最重要テーマである「OMO」について、その、基本概念から、具体的な、戦略、そして、私たちのキャリアへの、影響まで、あらゆる角度から、解説してきました。
オンラインと、オフライン。
デジタルと、リアル。
OMOは、これまで、二項対立で、語られがちだった、これらの、世界の、境界線を、完全に、溶かし去ります。
そして、その中心にあるのは、常に、「顧客」です。
顧客が、最も、心地よいと、感じる方法で、
顧客が、最も、便利だと、感じる場所で、
顧客が、最も、感動する、タイミングで、
最高の、おもてなしを、提供する。
OMOとは、その、「究極の、おもてなし」を、テクノロジーと、データの力で、実現しようとする、壮大で、しかし、極めて、人間的な、挑戦なのです。
- OMOは、分断された、顧客との接点を、一つの、滑らかな「旅」として、再編集する。
- OMOは、「マス(大衆)」に向けていた、企業の視線を、「個客(一人ひとり)」へと、フォーカスさせる。
- OMOは、店舗と、ECを、「競合」から、「最高の、パートナー」へと、変える。
- そして、OMOを、学ぶことは、あなた自身の、キャリアを、旧時代の、常識から、解放し、未来の、市場で、輝き続ける、人材へと、進化させる。
この、大きな、変革の時代。
変化を、恐れ、傍観者で、あり続けるのか。
それとも、変化の、波に乗り、自らが、新しい、顧客体験の、創造者となるのか。
その、選択が、あなたの会社の、そして、あなた自身の、未来を、決定づけることに、なるでしょう。
まずは、あなたの、会社の、顧客が、辿る「旅」を、想像してみることから、始めてみませんか?
その、旅の、どこかに、テクノロジーの力で、もっと、素敵にできる「瞬間」が、きっと、隠されているはずです。