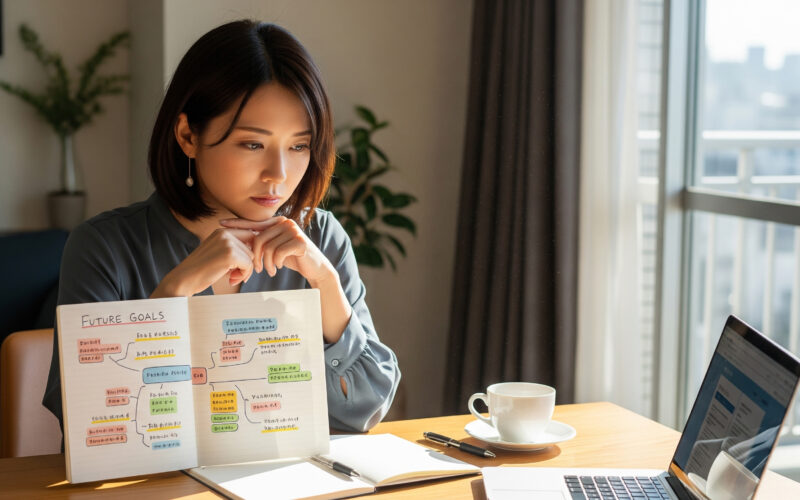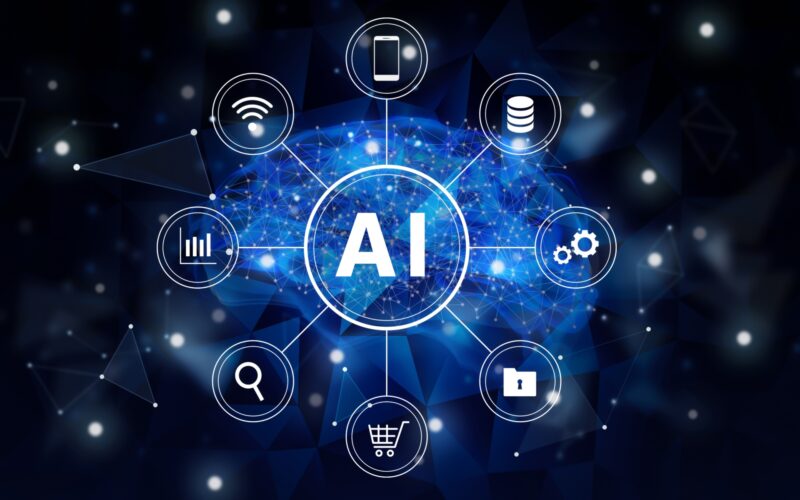はじめに:「お役所仕事」という、古い言葉が消える日
「この申請書を出すためだけに、仕事を半日休んで、市役所の窓口で、1時間も待たされた…」
「引っ越しの手続き、あちこちの窓口を、たらい回しにされて、本当に疲れた…」
「制度について、知りたいことがあっても、ウェブサイトの情報は、分かりにくいし、電話は、なかなかつながらない…」
このような、行政サービスに対する「不便」「不満」「不透明」といった、ネガティブな体験。
それは、民間企業が提供する、Amazonや、Uberのような、シームレスで、パーソナライズされた、デジタルサービスに慣れ親しんだ、私たちにとって、ますます、大きなストレスとなりつつあります。
この、国民の期待と、行政サービスの現実との間に、横たわる、深い溝を、テクノロジーの力で埋め、行政を、もっと、身近で、便利で、そして、信頼できる、パートナーへと、生まれ変わらせる、国家的な、一大プロジェクト。
それこそが、「自治体・行政サービスのDX(デジタルトランスフォーメーション)」、すなわち「デジタルガバメント」の、実現です。
この記事は、「行政のDXと聞いても、あまり、自分たちの生活や、ビジネスに関係ないと、感じている」「この、大きな変化の波の中で、どのような、新しい機会が、生まれているのか、知りたい」と考える、すべてのビジネスパーソンと、未来の社会を、担うリーダーのために書かれました。
本記事では、霞が関から、地方の市町村まで、日本全国で、今、静かに、しかし、確実に進んでいる、行政DXの、最前線を、体系的に、解き明かしていきます。
この記事を読み終える頃には、あなたは以下のものを手にしているはずです。
- なぜ今、行政のDXが、日本の、未来を左右する、最重要課題なのか、その本質的な理由
- マイナンバーカードの活用から、AIによる、住民相談まで、私たちの暮らしを、劇的に変える、具体的な、取り組みの全体像
- 「GovTech(ガブテック)」と呼ばれる、巨大な、新しいビジネス市場の、可能性
- そして、この、官民を巻き込んだ、変革の時代を、生き抜くために、求められるスキルと、未来のキャリアアップや転職に繋がる、明確なキャリアビジョン
行政のDXは、単なる、ITツールの導入では、ありません。
それは、社会の、OSそのものを、アップデートし、官民の、垣根を越えて、新しい価値を、共創していく、壮大な挑戦です。この、変革の、当事者となることは、最高のリスキリングであり、スキルアップの機会となります。
さあ、「お役所仕事」という、古い言葉が、過去のものとなる、その、歴史的な、転換点を、一緒に、目撃しましょう。
1. 自治体DXとは何か?単なる「電子化」との、決定的な違い
自治体・行政のDXを、単に「これまで、紙で行っていた手続きを、パソコンで、できるようにすること(電子化)」と、捉えているとしたら、その、革命性の、本質を、見誤るかもしれません。
DXが、目指すのは、既存の業務を、部分的に、デジタルツールに置き換える、といった、対症療法的な、改善に留まりません。
1-1. DXの本質は「住民(ユーザー)中心」への、意識・組織・文化の、全面的な変革
DXの本質は、テクノロジーを「手段」として、活用し、住民(ユーザー)の、利便性を、徹底的に、追求することを「目的」として、行政サービス、組織、業務プロセス、そして、職員の働き方や、文化そのものを、根本から、変革していくことにあります。
- 従来の「電子化(IT化)」:
- 視点:
行政「側」の、視点。「どうすれば、今の業務を、少しでも、効率化できるか」 - 例:
紙の申請書を、PDF化して、ウェブサイトから、ダウンロードできるようにする。(結局、印刷して、手書きし、郵送や、持参が、必要) - ゴール:
部分的な、業務の効率化。
- 視点:
- DXが目指すもの:
- 視点:
住民「側」の、視点。「どうすれば、住民が、最も、ストレスなく、簡単で、快適に、行政サービスを、利用できるか」 - 例:
スマートフォンアプリから、24時間365日、いつでも、申請が完結し、その後の、進捗状況も、リアルタイムで、確認できる。一度、入力した情報は、他の手続きで、再度、入力する必要がない(ワンスオンリー)。 - ゴール:
住民体験(CX – Citizen Experience)の、最大化と、社会全体の、生産性向上。
- 視点:
つまり、DXは、「行政中心」から「住民中心」へという、根本的な、パラダイムシフトなのです。
この、住民中心の、サービスを、デザインし、提供していくプロセスは、民間企業のWebマーケティングや、UXデザインの、考え方と、極めて、親和性が高い、領域です。
1-2. 国が、強力に推進する「デジタル庁」の、役割
この、国家的な、大改革を、強力に、牽引するために、2021年9月に、発足したのが「デジタル庁」です。
デジタル庁は、
- 国の、情報システムの、統括・監理
- 自治体の、情報システムの、標準化・共通化
- マイナンバー制度の、企画・立案
といった、権限を持ち、これまで、各省庁で、バラバラに、進められてきた、デジタル化の、取り組みを、国全体の、司令塔として、束ね、スピード感を持って、推進する、役割を担っています。
「誰一人、取り残さない、人に優しい、デジタル化を」という、ミッションの下、デジタル庁の、リーダーシップが、日本の、行政DXを、今、大きく、加速させているのです。
2. なぜ今、行政DXが、日本の「最重要課題」なのか?
行政のDXが、単なる、利便性向上の、ための取り組みに留まらず、日本の、社会と経済の、持続可能性そのものを、左右する、極めて重要な「国家課題」として、位置づけられているのは、なぜでしょうか。
その背景には、私たちが、直面する、避けては通れない、深刻な、社会構造の変化が、あります。
2-1. 課題①:超高齢社会と、生産年齢人口の、急激な減少
日本は、世界でも、前例のない、スピードで、超高齢社会に、突入しています。
これは、二つの、深刻な問題を、同時に、引き起こします。
- 社会保障サービスの、需要増大:
- 高齢者が、増えれば、年金、医療、介護といった、行政が提供する、社会保障サービスの、対象者と、そのニーズは、必然的に、増大します。
- 行政の「担い手」の、減少:
- その一方で、行政サービスを、提供する側である、地方公務員の数もまた、生産年齢人口の、減少に伴い、先細っていくことが、避けられません。
「増え続ける、サービス需要」と「減り続ける、人的リソース」。
この、絶望的とも言える、ギャップを、埋めるためには、もはや、従来通りの、人海戦術に、頼った、労働集約的な、行政運営では、立ち行かなくなります。
DXによって、定型的な、事務作業を、徹底的に、自動化・効率化し、限られた、人的リソースを、人間にしかできない、専門的な、相談業務や、創造的な、政策立案といった、より、付加価値の高い、業務に、再配分すること。
それが、質の高い、行政サービスを、維持し続けるための、唯一の道なのです。
2-2. 課題②:多様化する、住民ニーズと、新しい公共の、あり方
社会が、成熟し、人々の価値観が、多様化する中で、住民が、行政に求める、ニーズも、ますます、複雑化・個別化しています。
子育て、介護、防災、地域活性化…。
これらの、複雑な、社会課題に対して、行政だけで、全ての、解決策を、提供することは、もはや、困難です。
これからの、行政に求められるのは、自らが、全てのサービスを、提供する「プレイヤー」としてだけでなく、地域の、NPO、ボランティア団体、そして、民間企業といった、多様な主体が、連携し、協働するための「プラットフォーム(触媒)」としての、役割です。
行政DXは、
- オープンデータ:
行政が保有する、公共データを、誰もが、利用しやすい形で、公開し、民間企業が、それを活用した、新しいサービスを、創造することを、促す。 - 官民連携プラットフォーム:
地域の課題を、抱える住民と、それを解決できる、地域の、NPOや、企業を、オンラインで、マッチングさせる。
といった、テクノロジーの力で、官民連携(PPP – Public Private Partnership)を、加速させ、地域社会全体の、課題解決能力を、高めるための、強力な、基盤となります。
2-3. 課題③:激甚化する、自然災害と、危機管理への対応
地震、台風、豪雨といった、自然災害が、激甚化・頻発化する中で、住民の命と、財産を守るための、防災・減災対策は、自治体にとって、最重要の、責務です。
- 従来の課題:
- 災害発生時、避難所の開設情報や、被災状況といった、重要な情報が、電話や、FAX、職員の、足といった、アナログな手段で、伝達され、情報の、錯綜や、遅延が、発生していた。
- DXによる、解決策:
- リアルタイムな、情報伝達:
防災アプリや、SNS、エリアメールなどを、活用し、住民一人ひとりに、避難指示や、ハザードマップといった、パーソナライズされた、防災情報を、迅速かつ、確実に届ける。 - データに基づいた、被害予測:
AIが、リアルタイムの、気象データや、地形データを分析し、浸水エリアや、土砂災害のリスクを、高い精度で予測し、早期の、避難行動を、促す。 - ドローンによる、被災状況の把握:
人間が、立ち入れない、危険なエリアの、状況を、ドローンで、迅速に把握し、救助活動や、復旧計画の、立案に、役立てる。
- リアルタイムな、情報伝達:
行政DXは、住民の、日々の利便性を、高めるだけでなく、「万が一の時」に、住民の命を、守るための、生命線としての、役割も、担っているのです。
3. 【住民サービスのDX①】「行かなくていい、書かなくていい、待たなくていい」窓口へ
行政DXが、もたらす、最も分かりやすく、そして、多くの住民が、その恩恵を、実感できるのが、「窓口業務」の、変革です。
これまで、私たちの、時間と、労力を、奪ってきた、「行かないと、いけない」「紙に、書かないといけない」「長時間、待たないといけない」という、三重苦からの、解放が、今、始まっています。
3-1. マイナンバーカードが、全ての「鍵」になる
この、窓口革命の、中心的な役割を担うのが、「マイナンバーカード」です。
マイナンバーカードは、単なる、身分証明書では、ありません。それは、オンライン上で、確実な、本人確認を行うための「デジタルの鍵」であり、あらゆる、行政手続きの、入り口となる、重要なインフラです。
- マイナポータル:
- 政府が運営する、オンラインサービス。マイナンバーカードを、使って、ログインすることで、
- 子育てや、介護に関する、行政手続きの、オンライン申請(ぴったりサービス)。
- 自分の、所得や、税、年金に関する情報の、確認。
- 行政からの、お知らせ(児童手当の、現況届など)の、受け取り。
- といった、様々なサービスを、24時間365日、利用することができます。
- 政府が運営する、オンラインサービス。マイナンバーカードを、使って、ログインすることで、
3-2. オンライン申請と、電子申請:「行かなくていい」窓口
- オンライン申請:
- 転出・転入届、児童手当の申請、保育所の、入所申し込みといった、これまで、市役所の窓口で、行っていた、様々な手続きが、マイナポータルなどを通じて、スマートフォンや、PCから、オンラインで、完結できるようになります。
- 書かない窓口(スマート窓口):
- 全ての手続きが、オンラインで完結するのが、理想ですが、高齢者など、デジタルに不慣れな、住民のために、窓口業務そのものを、デジタル化する、取り組みも、進んでいます。
- 「書かない窓口」では、住民が、紙の申請書に、何度も、同じ情報を、手書きする必要は、ありません。職員が、住民から、聞き取りをしながら、タブレット端末に、情報を入力。住民は、その内容を、確認し、サインするだけ。
- マイナンバーカードを、提示すれば、氏名や、住所といった、基本情報は、自動で、入力されます。
- おくやみ窓口の、ワンストップ化:
- 家族が、亡くなった後の、手続きは、年金、保険、税金など、多岐にわたり、遺族は、複数の窓口を、たらい回しにされる、大きな負担を、強いられてきました。
- 「おくやみワンストップ窓口」では、一度の、手続きで、関連する、全ての、申請が、完了する、サービスが、多くの自治体で、導入されています。
3-3. AIチャットボットと、FAQシステム:「待たなくていい」窓口
- 従来の課題:
- 「粗大ごみの、出し方が、分からない」「児童手当の、申請に必要な書類は?」といった、住民からの、簡単な問い合わせが、電話で、殺到し、職員が、その対応に、追われ、本来の業務が、圧迫される。「電話が、なかなかつながらない」という、住民の不満も、大きい。
- DXによる、解決策:
- AIチャットボット:
自治体の、ウェブサイトや、LINE公式アカウントに、AIチャットボットを、設置。住民からの、よくある質問に対して、24時間365日、AIが、自動で、即座に回答します。 - FAQシステムの、最適化:
チャットボットに、寄せられた、質問データを分析し、「住民が、本当に、知りたいことは、何か」を、把握。その結果を、ウェブサイトの、FAQ(よくある質問)ページの、改善に、活かします。
- AIチャットボット:
これらの、テクノロジーは、住民の、自己解決率を、高め、職員を、定型的な、問い合わせ対応から、解放し、より、専門的な、相談が必要な、住民への、手厚いサポートに、リソースを集中させることを、可能にするのです。
4. 【住民サービスのDX②】子育て、教育、防災|暮らしの、あらゆる場面に、寄り添う
行政のDXは、窓口業務の、効率化だけに、留まりません。
子育て、教育、防災といった、私たちの、暮らしの、あらゆるシーンに、テクノロジーが、溶け込み、より、安全で、安心な、そして、豊かな、地域社会を、実現します。
4-1. 子育て支援の、DX
- 保育所の、利用調整(保活)の、オンライン化:
- 従来、紙の書類で、行われていた、保育所の、入所申し込みや、空き状況の確認、そして、複雑な、利用調整(入園選考)のプロセスを、オンライン化。
- 保護者の、負担を軽減すると同時に、自治体職員の、膨大な、事務作業を、効率化します。
- 母子健康手帳アプリ:
- 紙の、母子健康手帳を、電子化。
- 妊娠中からの、健康記録、子供の、成長記録(身長、体重など)、予防接種の、スケジュール管理などを、スマートフォンアプリで、一元管理。
- 自治体から、子供の月齢に合わせた、検診の案内や、子育て支援情報が、プッシュ通知で、届く。
- 子ども食堂や、地域の、遊び場の、情報発信:
- GIS(地理情報システム)を、活用し、地域の子育て関連施設や、イベント情報を、マップ上で、分かりやすく、提供する。
4-2. 教育の、DX(GIGAスクール構想)
- GIGAスクール構想:
- 全国の、小中学校の、児童・生徒に、一人一台の、学習者用PCと、高速大容量の、通信ネットワークを、一体的に整備する、国の、一大プロジェクト。
- もたらされる、教育の変革:
- 個別最適化された、学び:
AIドリルなどを、活用し、一人ひとりの、学習の進捗度や、理解度に合わせて、最適な、問題や、教材を提供する。 - 協働的な、学び:
クラウドツールを、活用し、グループでの、調べ学習や、プレゼンテーション作成といった、協働的な、学習活動を、活性化する。 - 遠隔教育:
都市部の、専門家と、地方の学校を、オンラインで繋ぎ、質の高い、授業を届けたり、不登校の、児童・生徒に、自宅からの、学習機会を、提供したりする。
- 個別最適化された、学び:
GIGAスクール構想は、単なる、デジタルデバイスの配布では、ありません。それは、これからの、予測困難な時代を、生き抜くために、必要な、情報活用能力や、創造性を、育むための、教育インフラの、再発明なのです。
4-3. 防災・見守りの、DX
- 防災情報の、パーソナライズ配信:
- 自治体の、防災アプリが、利用者の、現在地情報(GPS)や、事前に登録された、自宅の位置に基づき、その場所に、特化した、避難情報(開設されている、最寄りの避難所、浸水リスクなど)を、プッシュ通知で、配信する。
- デジタル・ハザードマップ:
- 地域の、浸水想定区域や、土砂災害危険箇所を、Web上の地図で、確認できる。AR技術を使い、スマホのカメラを、かざすと、現実の風景に、浸水した場合の、水位が、重ねて表示される、といった、サービスも登場しています。
- 高齢者の、見守りサービス:
- 高齢者宅に、設置された、IoTセンサー(電力使用量、ドアの開閉、人感センサーなど)が、生活リズムの、異常を検知すると、離れて暮らす家族や、地域の、民生委員に、自動で、通知を送る。
これらの、テクノロジーは、行政サービスを、より、プロアクティブ(先回り)で、パーソナル(一人ひとりに、寄り添う)なものへと、進化させていくのです。
5. 【行政内部のDX】「紙とハンコ」の文化から、データドリブンな組織へ
住民サービスの、華やかな変革を、裏側で支えるのが、行政内部の、徹底的な、業務改革です。
長年、行政組織に、深く根付いてきた「紙とハンコ」の文化や、縦割りの組織構造を、打ち破らなければ、真のDXは、成し遂げられません。
5-1. RPAによる、定型業務の、自動化
- RPA (Robotic Process Automation):
- 役割:
PC上で行われる、定型的な、クリックや、データ入力といった、単純作業を、ソフトウェアのロボットが、記憶し、人間の代わりに、自動で実行する技術。
- 役割:
- 行政における、活用例:
- 各種申請書の、内容を、基幹システムに、転記する作業。
- 複数の、Excelファイルから、データを集計し、定型の報告書を、作成する作業。
- 住民税の、課税・徴収に関する、通知書の、作成・発送作業。
- もたらされる価値:
- 職員を、単純作業から解放し、住民への、直接的な、サービス提供や、政策の企画・立案といった、より、付加価値の高い、コア業務に、集中させることができる。
- ヒューマンエラーの、削減と、業務品質の、向上。
5-2. AI-OCRによる、紙書類の、データ化
- AI-OCR (AI-Optical Character Recognition):
- 役割:
従来のOCR(光学的文字認識)を、AI技術で、進化させ、手書きの文字や、非定型の帳票であっても、高い精度で、読み取り、テキストデータ化する技術。
- 役割:
- 行政における、活用例:
- 住民から、提出される、手書きの、各種申請書や、アンケート用紙を、スキャンし、その内容を、自動で、データ化する。
- もたらされる価値:
- 紙媒体を、起点とした、業務プロセスにおける、データ入力の、ボトルネックを、解消する。
5-3. ガバメントクラウドと、システムの標準化
- 従来の課題:
- 全国の、約1,700の、地方自治体が、それぞれ、独自の仕様で、個別に、情報システムを、開発・運用してきた。
- これにより、システム間の、データ連携が、困難になったり、国からの、新しい制度(給付金など)への、迅速な対応が、遅れたり、自治体ごとに、多大な、開発・運用コストがかかったり、といった、多くの問題が、生じていました。
- DXによる、解決策:
- ガバメントクラウド:
政府が、整備する、共通の、クラウドサービス利用環境。自治体は、この、セキュアな、クラウド基盤上で、業務を行う。 - 基幹業務システムの、標準化:
住民基本台帳、税、社会保障といった、全国の自治体で、共通して行われる、17の基幹業務について、国が、システムの「標準仕様」を、定めます。
各自治体は、2025年度末までに、この、標準仕様に、準拠したシステムへと、移行することが、求められています。
- ガバメントクラウド:
- もたらされる価値:
- 自治体間の、データ連携の、円滑化。
- システム開発・運用コストの、大幅な削減。
- ITベンダーへの、過度な依存からの、脱却。
5-4. EBPM (証拠に基づく、政策立案)
- EBPM (Evidence-Based Policy Making):
- 役割:
政策の、企画・立案において、担当者の、経験や勘だけでなく、客観的な、データ(証拠)に基づいて、合理的な、意思決定を行う、というアプローチ。
- 役割:
- DXとの、関係:
- 行政の、各分野で、デジタル化が進み、データが蓄積されていくことで、このEBPMを、本格的に、実践するための、土壌が、整います。
- 活用例:
- 地域の、人流データや、公共交通の、利用データを分析し、最適な、バス路線の、再編を、検討する。
- 過去の、救急出動データと、地域の、人口動態データを、掛け合わせ、将来の、救急需要を予測し、救急隊の、最適な配置を、計画する。
これらの、内部改革は、行政組織を、硬直的な、官僚組織から、データに基づいて、柔軟に、自己変革し続ける「学習する組織」へと、進化させていくのです。
6. 行政DXの、課題と、乗り越えるべき壁
行政DXは、日本の、未来にとって、不可欠な、改革ですが、その道のりは、決して、平坦では、ありません。
民間企業の、DX以上に、複雑で、根深い、いくつかの「壁」が、その前に、立ちはだかります。
6-1. デジタルデバイド(情報格差)への、配慮
- 課題:
- 行政サービスは、全ての住民に、あまねく、公平に、提供されなければならない、という、大原則があります。
- スマートフォンや、PCを、使いこなせる、若者世代と、デジタルに、不慣れな、高齢者との間には、大きな「デジタルデバイド(情報格差)」が、存在します。
- デジタル化を、急ぐあまり、デジタルが使えない人々を、取り残してしまうことは、絶対にあってはなりません。
- 乗り越え方:
- 誰一人、取り残さない、多様な、チャネルの維持:
オンライン申請を、推進する一方で、電話、郵送、そして、対面の窓口といった、従来からの、チャネルも、当面の間、維持し、住民が、自分に合った方法を、選択できるようにする。 - デジタル活用支援員の、配置:
地域の、公民館や、図書館などで、高齢者向けに、スマートフォンの、使い方教室を、開催したり、オンライン申請の、操作を、手助けする「デジタル活用支援員」を、配置したりする。
- 誰一人、取り残さない、多様な、チャネルの維持:
6-2. 縦割り行政の、壁
- 課題:
- 日本の、行政組織は、省庁、都道府県、市町村、そして、各組織内の、部署ごとに、業務と、権限が、細かく、分断された「縦割り行政」が、長年の課題となっています。
- この、縦割りの壁が、組織を、横断した、データ連携や、ワンストップサービスの、実現を、阻む、大きな障壁となります。
- 乗り越え方:
- デジタル庁による、トップダウンの改革:
前述の、ガバメントクラウドや、システムの標準化は、この縦割りの壁を、トップダウンで、打ち破るための、強力な、取り組みです。 - CDO(最高デジタル責任者)の、設置:
各自治体に、デジタル戦略の、最高責任者である「CDO」を、設置し、部署の、利害を超えて、全庁的な、改革を、推進する、リーダーシップを発揮する。
- デジタル庁による、トップダウンの改革:
6-3. セキュリティと、プライバシーの、確保
- 課題:
- 行政が、扱う、住民のデータは、個人情報の中でも、特に、機微な情報を、多く含みます。
- デジタル化、データ連携が進めば進むほど、サイバー攻撃による、情報漏洩のリスクは、増大します。
- 乗り越え方:
- 堅牢な、セキュリティ基盤の、構築:
ガバメントクラウドなど、国の基準を満たした、高度な、セキュリティ環境を、活用する。 - プライバシー・バイ・デザイン:
新しい、サービスを設計する、初期段階から、プライバシー保護の、観点を、組み込む。
- 堅牢な、セキュリティ基盤の、構築:
6-4. 深刻な「デジタル人材不足」
- 課題:
- この、壮大な、行政DXを、推進するための「デジタル人材」が、行政の内部に、圧倒的に、不足しています。
- 乗り越え方:
- 民間からの、専門人材の登用:
IT企業や、コンサルティングファームなど、民間企業で、活躍してきた、DXのプロフェッショナルを、CDOや、専門官として、積極的に、登用する。 - 既存職員の「リスキリング」:
最も、持続可能な、解決策は、内部の職員を、育てることです。次章で、詳しく解説します。
- 民間からの、専門人材の登用:
7. 行政DX時代の、新しい「公務員」と、求められるキャリア
行政DXの、急速な進展は、「公務員」という、仕事の、あり方と、そこで、求められるスキルを、大きく、変えていきます。
もはや、「安定」だけを、求めて、公務員になる、という時代は、終わりを告げようとしています。
7-1. 求められるのは「サービスデザイナー」としての、視点
これからの、公務員に、求められるのは、単に、法律や、条例に基づいて、決められた業務を、正確に、こなすだけの「事務処理の、専門家」では、ありません。
- 求められる、新しい役割:
- 住民(ユーザー)の、課題に、深く共感し、
- テクノロジーの、可能性を、理解し、
- 官民の、多様な、ステークホルダーを、巻き込みながら、
- 本当に、価値のある、新しい、公共サービスを、デザインし、実現していく「サービスデザイナー」であり、「社会起業家」としての、役割です。
この、新しい役割を、担うためには、従来の、法律の知識に加えて、新しいスキルセットを、積極的に、学び、身につけていく「リスキリング」が、不可欠となります。
- 求められる、新しいスキルセット:
- UX(ユーザー体験)デザイン
- データ分析
- プロジェクトマネジメント
- Webマーケティング的な、広報・コミュニケーション能力
7-2. 公務員の「リスキリング」と、新しいキャリアパス
多くの、自治体では、職員の、デジタルリテラシーを、向上させるための、リスキリングの、取り組みが、始まっています。
この、学びの機会を、主体的に、活用し、新しいスキルを、身につけた職員には、これまでにない、多様で、魅力的な、キャリアアップの、道が、拓けています。
- デジタル戦略担当、DX推進室:
- 自治体の、DX戦略の、立案と、実行を、リードする、中核部署で、活躍する。
- データサイエンティスト:
- EBPMを、推進するための、データ分析の、専門家として、キャリアを築く。
- 官民連携の、リエゾン(橋渡し役):
- 民間企業との、協業プロジェクトを、推進する、専門官。
7-3. 民間人材にとっての、新しい「転職」先としての、公務員
この、行政DXの、大きな波は、民間企業で、活躍してきた、プロフェッショナルにとっても、大きな、転職の、チャンスを、意味します。
- CDO(最高デジタル責任者)、CIO(最高情報責任者):
- 民間企業で、培った、経営や、テクノロジーの、知見を、活かし、自治体の、トップマネジメントとして、改革を、リードする。
- 任期付き、職員 / 専門委員:
- 特定の、プロジェクト(例:スマートシティの、推進)のために、数年間の、任期付きで、専門知識を、提供する。
「社会を、より良くしたい」という、強い想いを持つ、ビジネスパーソンにとって、行政の現場は、その、スキルと、情熱を、社会に、直接、還元できる、極めて、やりがいの大きい、新しい「挑戦の場」となりつつあるのです。
8. まとめ:行政DXは、「社会」の、デジタルトランスフォーメーション
本記事では、自治体・行政サービスのDXという、私たちの、暮らしの、土台を、大きく変えるテーマについて、その、基本概念から、具体的な、取り組み、そして、私たちのキャリアへの、影響まで、あらゆる角度から、解説してきました。
行政DXは、単に、役所の仕事を、効率化するだけの、話では、ありません。
その本質は、テクノロジーの力で、行政と、住民、そして、民間企業との、関係性を、再構築し、より、オープンで、より、協働的な、新しい「社会の、OS」を、創り上げていく、壮大な、プロジェクトなのです。
- 行政DXは、「情報の壁」を壊し、行政を、より、透明で、信頼できる、存在へと、変える。
- 行政DXは、「手続きの壁」を壊し、私たちの、貴重な、時間を、取り戻してくれる。
- 行政DXは、「組織の壁」を壊し、官民が、連携して、地域の課題を、解決する、新しい「協働」の、形を生み出す。
- そして、この、変革の、当事者となることは、あなた自身の、キャリアを、社会的な、価値創造へと、直結させる、最高の「スキルアップ」である。
この、大きな、変革の時代。
私たち、一人ひとりが、単なる、行政サービスの「受け手」として、傍観するのではなく、
「もっと、こうすれば、良くなるのに」と、主体的に、声を上げ、
そして、時には、自らが、「担い手」として、その変革の、渦の中に、飛び込んでいく。
その、市民一人ひとりの、小さな、当事者意識こそが、日本の、行政を、そして、社会全体を、より、しなやかで、豊かな、未来へと、導く、大きな、原動力となるはずです。