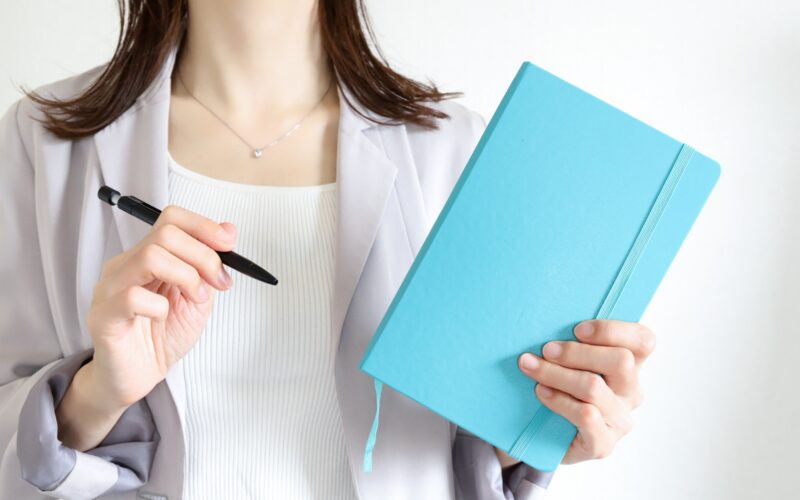「リスキリング」—。
数年前までは一部の専門家の間で使われる言葉でしたが、今やニュースやビジネスシーンで聞かない日はないほど、社会全体を巻き込む巨大なキーワードとなりました。政府は「人への投資」として1兆円規模の予算を掲げ、企業はこぞってリスキリングプログラムを導入しています。
しかし、なぜ今、これほどまでに日本中で「リスキリング」が叫ばれているのでしょうか?
それは、単なる一過性のブームではありません。私たちの足元で静かに、しかし確実に進行してきた、日本社会の構造的な変化が限界点を迎え、もはや避けては通れない国家的課題として顕在化した結果なのです。
この記事では、今の日本でリスキリングが不可欠とされる「5つの社会的背景」を、マクロな視点から深掘りしていきます。この大きな変化の全体像を理解することは、個人が自身のキャリアアップやスキルアップを考える上で、極めて重要な羅針盤となるはずです。
テクノロジーの進化と人口構造の変化という「避けられない波」
まず、私たちが直面しているのは、個人の努力や一企業の戦略だけでは抗うことのできない、地球規模の「テクノロジーの進化」と、日本特有の「人口構造の変化」という、二つの巨大な波です。
第四次産業革命とDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速
AI、IoT、ビッグデータといった技術が社会のあらゆる領域に浸透する「第四次産業革命」の到来は、仕事のあり方を根本から変えつつあります。これまで人間が行っていた定型的な業務は自動化され、代わりにデータを分析・活用する能力や、新しいビジネスを創造する能力が求められるようになりました。
この変化に対応し、企業の競争力を高める取り組みが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。しかし、日本のDXは欧米諸国に比べて遅れていると指摘されており、多くの企業が強い危機感を抱いています。
この遅れの最大の原因が、DXを推進できるデジタル人材の圧倒的な不足です。特に、データに基づいた戦略的な顧客アプローチを設計・実行できるWebマーケティング人材や、AIを扱えるエンジニアは、採用市場での獲得競争が激化しています。
結果として、企業は外部採用だけに頼るのではなく、既存社員に新しいデジタルスキルを習得してもらう「リスキリング」に活路を見出しました。これは、既存の業務知識を持つ社員がデジタルスキルを身につけることで、より実践的で効果的なDXが実現できるという期待も込められています。もはやリスキリングは、一部のIT企業だけのものではなく、あらゆる業界の企業にとって、生き残りをかけた必須の経営戦略となっているのです。
深刻な労働人口減少と生産性の課題
日本のもう一つの避けられない現実が、少子高齢化による「労働人口の減少」です。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は、2020年の約7,400万人から、2050年には約5,200万人へと、30年間で2,000万人以上も減少すると予測されています。
働き手の数が減り続ける中で、国全体の経済規模を維持・成長させるためには、もはや選択肢は一つしかありません。それは、「労働者一人ひとりの生産性を向上させること」です。
一人の人間が、より付加価値の高い仕事、より創造的な仕事ができるようにならなければ、日本経済は縮小均衡に陥ってしまいます。そのために不可欠なのが、リスキリングです。
例えば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化するRPAツールを導入し、空いた時間でそのデータを分析し、マーケティング戦略を立案する。これは、まさにリスキリングによる生産性向上の典型例です。
働き手の「数」が減るという制約があるからこそ、一人ひとりの「質」を高めるスキルアップが国家的な急務となり、その最も有効な手段としてリスキリングが強力に推進されているのです。
日本型システムの限界とグローバル化の挑戦
日本の社会経済を長らく支えてきた伝統的な「日本型雇用システム」が、その役目を終えつつあります。この内部構造の変化と、外部からのグローバルな競争圧力も、リスキリングの必要性を高める大きな要因です。
終身雇用・年功序列の崩壊と「ジョブ型雇用」への移行
かつての日本企業は、「メンバーシップ型雇用」が主流でした。これは、新卒で一括採用した社員を、定年まで面倒を見る「終身雇用」を前提とし、年齢と共に給与が上がる「年功序列」で処遇する仕組みです。このシステムの中では、社員は会社の指示で様々な部署を経験するジェネラリストとして育成され、個人の専門性よりも会社への忠誠心が重視されました。
しかし、バブル崩壊後の長期的な経済停滞や、グローバル競争の激化により、企業はこの手厚い雇用形態を維持できなくなりました。大企業でさえ早期退職を募集する時代となり、終身雇用は事実上崩壊したと言えます。
それに代わって注目されているのが、欧米で主流の「ジョブ型雇用」です。これは、特定の職務(ジョブ)に対して求められるスキルや経験を明確にし、その職務を遂行できる人材を採用・配置する仕組みです。ここでは年齢や勤続年数ではなく、その人が持つ「専門スキル」が評価の基準となります。
この移行は、働く私たちに大きな変化を迫ります。もはや、会社にぶら下がっていれば安泰という時代は終わり、自らのスキルによってキャリアを切り拓く必要が出てきたのです。特定の分野で高い専門性を持つ人材が評価されるため、自律的なスキルアップが不可欠となり、キャリアチェンジを目指す際には、目標とする職務に合わせたリスキリングを通じて、戦略的に転職市場での価値を高めることが常識となりつつあります。
激化する国際競争と日本の産業構造の遅れ
かつて「モノづくり大国」として世界を席巻した日本の産業ですが、近年、その国際競争力の低下が指摘されています。スイスのビジネススクールIMDが発表する「世界競争力年鑑」では、日本の順位は長期的に低迷傾向にあります。
特に、デジタル分野や、企業の変革に対する俊敏性といった項目での評価が低く、日本の産業構造が世界の潮流から遅れを取っていることが浮き彫りになっています。
この状況を打開し、グローバル市場で再び輝きを取り戻すためには、産業構造そのものを、より付加価値の高いデジタルサービスやソリューションを提供する形へと転換していく必要があります。そして、その変革を担うのは、間違いなく「人」です。
世界レベルで戦えるWebマーケティング戦略を描ける人材、国際標準のソフトウェアを開発できるエンジニア、グローバルなサプライチェーンを最適化できるデータサイエンティスト。このような高度な専門性を持つ人材を一人でも多く育成することが、日本の産業界全体の課題となっています。国や企業が主導するリスキリングには、個人のキャリアアップ支援という側面だけでなく、日本の国際競争力を再興するための「人材インフラ投資」という、極めて戦略的な狙いがあるのです。
個人の価値観の変化と「キャリア自律」の時代
ここまでの4つの背景は、主に社会や企業といったマクロな視点からの変化でした。しかし、最後の5つ目の背景は、私たち働く個人の「内面的な変化」です。この個人の価値観の変化が、リスキリングの大きな潮流を内側から後押ししています。
「人生100年時代」における働き方の多様化とキャリアの長期化
医療の進歩などにより「人生100年時代」が現実のものとなり、私たちの職業人生は、かつての「60歳定年」モデルとは比べ物にならないほど長期化しています。40年、50年と働き続ける中で、一つの会社、一つの職種だけでキャリアを終えることは、むしろ稀になるでしょう。
この長いキャリアを充実させるためには、ライフステージの変化(結婚、出産、介護など)や、自身の興味関心の変化に合わせて、働き方を柔軟に変えていく必要があります。時には、一度キャリアを中断して学び直したり、全く新しい分野に挑戦したりといった、大胆なキャリアチェンジも選択肢に入ってきます。
このようなキャリアの複線化・長期化を前提とすると、一度身につけたスキルだけで逃げ切ることは不可能です。社会の変化や自身の状況に応じて、必要なスキルを学び直し、自分自身をアップデートし続けるリスキリングは、長い職業人生を生き抜くための「生涯学習」として、全ての人にとって必須の営みとなったのです。
会社への依存から「個の確立」へ:キャリア自律の希求
終身雇用の崩壊と連動して、人々のキャリアに対する価値観も大きく変化しました。特に若い世代を中心に、会社にキャリアを委ねるのではなく、「自分のキャリアは自分で創る」という「キャリア自律」の意識が急速に高まっています。
彼らが仕事に求めるのは、安定した給与だけでなく、自身の「成長実感」や「社会への貢献実感」、そして「柔軟な働き方」です。会社はもはや運命共同体ではなく、自身のスキルアップやキャリア目標を実現するための「プラットフォーム」の一つとして捉えられています。
このキャリア自律の意識は、主体的なリスキリングへの強力な動機となります。会社が機会を与えてくれるのを待つのではなく、自らの市場価値を高めるために、積極的に新しい知識やスキルを学ぶ。そして、そのスキルを武器に、社内でのキャリアアップを目指したり、より良い環境を求めて転職したりといった選択肢を、常に持っておきたいと考えています。
この個人の内発的な「成長意欲」と、これまで見てきた社会や企業の「リスキリング推進」の動きが合流したことで、今の日本に、かつてないほどの学びのムーブメントが生まれているのです。
5つの波を乗りこなし、自らの手で未来を築く
この記事では、なぜ今、日本で「リスキリング」がこれほどまでに叫ばれているのか、その背景にある5つの大きな社会的変化を解説してきました。
リスキリングを促す5つの社会的背景
- DXの加速: テクノロジーの進化が、仕事に求められるスキルを根本から変えている。
- 労働人口の減少: 働き手の「数」を「質」で補うため、一人ひとりの生産性向上が急務。
- 日本型雇用の崩壊: 会社依存のキャリアが終わり、個人の「専門スキル」が問われる時代へ。
- 国際競争の激化: 日本の産業が世界で再び勝つため、人材の高度化が不可欠。
- 個人の価値観の変化: 「キャリア自律」の意識が高まり、主体的な学びが求められている。
これら5つの変化は、それぞれが独立しているのではなく、互いに複雑に絡み合いながら、私たち一人ひとりのキャリアに影響を与える巨大な波となっています。
この大きな時代のうねりを、ただ翻弄されるだけの受け身の存在でいるのか。それとも、変化の本質を理解し、リスキリングというサーフボードを手に、波を乗りこなしていくのか。選択は、私たち自身に委ねられています。
確かなことは、この変化はもはや誰にも止められないということです。そして、この変化の中には、これまでの常識や序列が通用しなくなるという危機と同時に、意欲ある個人が自らの手でキャリアを切り拓ける、大きなチャンスが眠っています。この記事が、そのチャンスを掴むための一助となれば幸いです。